はりねずみが眠るとき
昼寝をしながら本を読み、ビールを空けて料理する日々
「まあいいか」で、いこう
東京駅の前、KITTEで友人とランチした。
夏休みだし、ちょっと贅沢してフレンチでも食べようかという話になり、軽いランチのコースを選び、ふたりのんびりとした気分での食事会となった。
彼女とは年に何度か会って、とりとめもなく近況を語り合う仲だ。彼女がご主人の転勤先のロサンジェルスにいる頃、娘を連れて遊びに行ったのは、もう5年ほど前になるだろうか。おたがい子ども達の年齢が変わらないこともあり、また何日かお世話になり、ご主人やお嬢さんともわいわいと過ごさせてもらったこともあり、しばらく会っていなくとも話ははずむ。楽しい時間だった。
いつもまじめで、何事も誠実に取り組む彼女を、わたしはとても尊敬している。何かを選択しなくてはならないとき、彼女だったらどうするだろうかと考え、決めることもある。だから、ごく普通であるその言葉は、意外な輝きを放って、わたしの胸に届いた。
「最近、まあいいか、って思うことも大切だって思うようになったのよ」
その言葉を聞き、精一杯やっている人の「まあいいか」は、眩しいんだなと思った。わたしの口癖であるその言葉は、しかし口癖であってもなかなかそうは思えない場合も多く、わたしとてつまらないことで悩んだりもするのだ。
「まあいいかで、いこうね」
彼女は、別れ際、再びそう言って手を振った。そのとき、わたしのなかで使い古された「まあいいか」は、新しい意味を持つものとして生まれ変わった。
「まあいいか」
ゆっくり噛みしめると、思い悩んでいたことすべてが解けていく気がした。

前菜は3種類。赤紫蘇のグラニテ。マスカルポーネチーズをのせて。

スモークサーモンと何種類かのトマト。ベースはガスパチョです。

栗と南瓜のスープ仕立て。フォアグラとアーモンドも入っていました。

メインは、穴子のフリットと茄子ととうもろこし。カレー風味でした。

デザートのブランマンジェと、フランボワーズのシャーベット。
甘いモノが苦手なわたしにも、美味しく食べられました。
たぶんルバーブの酸味が、しっかりと効いていたからです。

夏休みだし、ちょっと贅沢してフレンチでも食べようかという話になり、軽いランチのコースを選び、ふたりのんびりとした気分での食事会となった。
彼女とは年に何度か会って、とりとめもなく近況を語り合う仲だ。彼女がご主人の転勤先のロサンジェルスにいる頃、娘を連れて遊びに行ったのは、もう5年ほど前になるだろうか。おたがい子ども達の年齢が変わらないこともあり、また何日かお世話になり、ご主人やお嬢さんともわいわいと過ごさせてもらったこともあり、しばらく会っていなくとも話ははずむ。楽しい時間だった。
いつもまじめで、何事も誠実に取り組む彼女を、わたしはとても尊敬している。何かを選択しなくてはならないとき、彼女だったらどうするだろうかと考え、決めることもある。だから、ごく普通であるその言葉は、意外な輝きを放って、わたしの胸に届いた。
「最近、まあいいか、って思うことも大切だって思うようになったのよ」
その言葉を聞き、精一杯やっている人の「まあいいか」は、眩しいんだなと思った。わたしの口癖であるその言葉は、しかし口癖であってもなかなかそうは思えない場合も多く、わたしとてつまらないことで悩んだりもするのだ。
「まあいいかで、いこうね」
彼女は、別れ際、再びそう言って手を振った。そのとき、わたしのなかで使い古された「まあいいか」は、新しい意味を持つものとして生まれ変わった。
「まあいいか」
ゆっくり噛みしめると、思い悩んでいたことすべてが解けていく気がした。
前菜は3種類。赤紫蘇のグラニテ。マスカルポーネチーズをのせて。
スモークサーモンと何種類かのトマト。ベースはガスパチョです。
栗と南瓜のスープ仕立て。フォアグラとアーモンドも入っていました。
メインは、穴子のフリットと茄子ととうもろこし。カレー風味でした。
デザートのブランマンジェと、フランボワーズのシャーベット。
甘いモノが苦手なわたしにも、美味しく食べられました。
たぶんルバーブの酸味が、しっかりと効いていたからです。
『うつくしい人』
西加奈子『うつくしい人』(幻冬舎文庫)を、読んだ。
自己顕示に苛まれ、常に他人の目を気にして生きてきた百合は、29歳。つまらないミスから会社を辞めてしまい、焦燥感にいてもたってもいられなくなり、浮世離れした離島のホテルで数日過ごそうと旅に出る。
百合の背後に、幼い頃からあったもの。それは、優等生で美しい姉の存在だった。しかし、その姉も高校時代にいじめにあってから家に引きこもっている。姉のようにはならず、社会に出てきちんと生活している自分を心の支えにしてきた百合だが、仕事を失くし、いとも簡単に心のバランスは崩れていった。
そんな気持ちを抱えた百合は、旅先の離島のホテルで、そこで働くバーテン坂崎と、ひとり旅するドイツ人マティアスに出会う。彼らも彼らの悩みを抱えていて、百合はそれを自分のものとは交わることのない平行なものだと知りながらも、彼らと過ごす時間に、心が解き放たれていくのを感じていた。
以下、客が置いていった本を貯蔵してある図書館で、3人が本に挟まった写真を探すシーンから。
「うーん。でも、本を置きに来るんです。吸収するだけじゃなくて、置いていくことも必要なのかもしれない、と思います」
坂崎は、しみじみとそう言った。何故かその言葉は、私の頭に素直に入ってきた。吸収すること、身につけることだけが、人間にとって尊い行為なのではない。なにかをかなぐり捨て、忘れていくことも、大切なのだ。
百合には、この図書館が、本だけではなく心の錘を置いていく場所だと思えた。もしかしたら人は、そういう場所を求めて旅をするのかも知れない。そしてそれは、たぶん場所ではない。錘を置いていける時かどうかは、その人にしか判らなくて、その時を探して旅をするのだと、読み終えてしみじみ考えた。

「うつくしい」とは言えないような、顔をしかめた表情のふたり。
なのに何故だか、とても魅力的に映る女性達の絵です。
読み終えてから見ると、読む前とは違った印象を受けました。

自己顕示に苛まれ、常に他人の目を気にして生きてきた百合は、29歳。つまらないミスから会社を辞めてしまい、焦燥感にいてもたってもいられなくなり、浮世離れした離島のホテルで数日過ごそうと旅に出る。
百合の背後に、幼い頃からあったもの。それは、優等生で美しい姉の存在だった。しかし、その姉も高校時代にいじめにあってから家に引きこもっている。姉のようにはならず、社会に出てきちんと生活している自分を心の支えにしてきた百合だが、仕事を失くし、いとも簡単に心のバランスは崩れていった。
そんな気持ちを抱えた百合は、旅先の離島のホテルで、そこで働くバーテン坂崎と、ひとり旅するドイツ人マティアスに出会う。彼らも彼らの悩みを抱えていて、百合はそれを自分のものとは交わることのない平行なものだと知りながらも、彼らと過ごす時間に、心が解き放たれていくのを感じていた。
以下、客が置いていった本を貯蔵してある図書館で、3人が本に挟まった写真を探すシーンから。
「うーん。でも、本を置きに来るんです。吸収するだけじゃなくて、置いていくことも必要なのかもしれない、と思います」
坂崎は、しみじみとそう言った。何故かその言葉は、私の頭に素直に入ってきた。吸収すること、身につけることだけが、人間にとって尊い行為なのではない。なにかをかなぐり捨て、忘れていくことも、大切なのだ。
百合には、この図書館が、本だけではなく心の錘を置いていく場所だと思えた。もしかしたら人は、そういう場所を求めて旅をするのかも知れない。そしてそれは、たぶん場所ではない。錘を置いていける時かどうかは、その人にしか判らなくて、その時を探して旅をするのだと、読み終えてしみじみ考えた。
「うつくしい」とは言えないような、顔をしかめた表情のふたり。
なのに何故だか、とても魅力的に映る女性達の絵です。
読み終えてから見ると、読む前とは違った印象を受けました。
油を拭くぼろきれ
調理後のフライパンの油を拭くのに、ぼろきれを使っている。
今、使っているのは、わたし用の古いバスタオルを小さく切ったものだ。そろそろそれがなくなるので新しいものを作ろうと、ぼろきれを集めたかごを探すと、娘が使っていた古いバスタオルが出てきた。
カナダにいる上の娘のものである。
あまりゲンを担いだりする方ではないが、なんとなく彼女が使っていたと思うと、そのすり切れたバスタオルを切ろうという気持ちにはなれなかった。べつにそのタオルを切って油を拭いたからと言って、娘に何が起こるという訳でもないのだと判ってはいるが、ただ切る気になれなかったのだ。
ぼろきれは他にもある。古いシャツなどで新しい小布を作りつつ、親というものは、と半ば呆れながらも胸に温かいものが流れるのを感じた。
「10月の初旬に、日本に帰るチケットをとったよ」
その娘からメールが来た。彼女の1年3か月の旅も、もうすぐ終わる。そしてまた何処かへ出かけて行くのだろう。彼女のバスタオルで小布を作るのは、帰って来てから、そして何処かへ旅立つ前にしようと、メールを読み考えた。

フライパンの油を吸い取ってくれる、古いタオル達に感謝です。

夕べは、お好み焼きを焼きました。ホットプレートの油も、
ぼろきれで作った小布が、綺麗に拭いてくれます。

今、使っているのは、わたし用の古いバスタオルを小さく切ったものだ。そろそろそれがなくなるので新しいものを作ろうと、ぼろきれを集めたかごを探すと、娘が使っていた古いバスタオルが出てきた。
カナダにいる上の娘のものである。
あまりゲンを担いだりする方ではないが、なんとなく彼女が使っていたと思うと、そのすり切れたバスタオルを切ろうという気持ちにはなれなかった。べつにそのタオルを切って油を拭いたからと言って、娘に何が起こるという訳でもないのだと判ってはいるが、ただ切る気になれなかったのだ。
ぼろきれは他にもある。古いシャツなどで新しい小布を作りつつ、親というものは、と半ば呆れながらも胸に温かいものが流れるのを感じた。
「10月の初旬に、日本に帰るチケットをとったよ」
その娘からメールが来た。彼女の1年3か月の旅も、もうすぐ終わる。そしてまた何処かへ出かけて行くのだろう。彼女のバスタオルで小布を作るのは、帰って来てから、そして何処かへ旅立つ前にしようと、メールを読み考えた。
フライパンの油を吸い取ってくれる、古いタオル達に感謝です。
夕べは、お好み焼きを焼きました。ホットプレートの油も、
ぼろきれで作った小布が、綺麗に拭いてくれます。
京野菜、万願寺とうがらし
夏になると毎年、生協で万願寺とうがらしを注文する。
とうがらしの形をそのまま大きくしたような緑の美しい野菜だが、全く辛くない。シシトウなどは、たまにものすごく辛いものが混じっていたりするが、そういう心配は皆無だ。ピーマンなどより余程甘く種も少ないので、大きいまま素揚げにして、かぶりついて楽しんでいる。塩味も合うし、出汁つゆに浸けても美味い。京都府が認定している「ブランド京野菜」のひとつだそうだ。
京都という土地は、不思議な場所である。修学旅行で、または個人で訪ねたことがある、という人がほとんどだろう。わたし自身、やはり何度も行っている。夫の実家である神戸に帰省した際に、ちょっと立ち寄ることができることが大きいかとは思うのだが。
旅行として行ったのは、上の娘が中学を卒業したときだった。末娘は小学6年になる春で、神戸の義母を誘い、女ばかり4人で哲学の道を歩いたことを思い出す。上の娘は中学卒業と同時に、思春期の反抗期も卒業していて、義母も一緒に楽しんでもらい、とても気持ちのいい旅だった。十年も前のことになる。
京野菜が、特別なものであるような気がするのは、多くの人のなかにある旅の記憶が生むものなのだろうか。それとも、特別な土地であるという京都の人々の意識が生むものなのだろうか。どちらにしろ、京野菜である万願寺とうがらしを思いっきりかぶりつくのが、夏の楽しみのひとつになっている。

農家さんにいただいた茄子と。万願寺とうがらし、立派です。

素揚げにして、出汁つゆに浸けました。本物の唐辛子も1本入れて。

とうがらしの形をそのまま大きくしたような緑の美しい野菜だが、全く辛くない。シシトウなどは、たまにものすごく辛いものが混じっていたりするが、そういう心配は皆無だ。ピーマンなどより余程甘く種も少ないので、大きいまま素揚げにして、かぶりついて楽しんでいる。塩味も合うし、出汁つゆに浸けても美味い。京都府が認定している「ブランド京野菜」のひとつだそうだ。
京都という土地は、不思議な場所である。修学旅行で、または個人で訪ねたことがある、という人がほとんどだろう。わたし自身、やはり何度も行っている。夫の実家である神戸に帰省した際に、ちょっと立ち寄ることができることが大きいかとは思うのだが。
旅行として行ったのは、上の娘が中学を卒業したときだった。末娘は小学6年になる春で、神戸の義母を誘い、女ばかり4人で哲学の道を歩いたことを思い出す。上の娘は中学卒業と同時に、思春期の反抗期も卒業していて、義母も一緒に楽しんでもらい、とても気持ちのいい旅だった。十年も前のことになる。
京野菜が、特別なものであるような気がするのは、多くの人のなかにある旅の記憶が生むものなのだろうか。それとも、特別な土地であるという京都の人々の意識が生むものなのだろうか。どちらにしろ、京野菜である万願寺とうがらしを思いっきりかぶりつくのが、夏の楽しみのひとつになっている。
農家さんにいただいた茄子と。万願寺とうがらし、立派です。
素揚げにして、出汁つゆに浸けました。本物の唐辛子も1本入れて。
夏のウグイス
昨日の朝は、ぐっと気温が下がった。
寒い、と感じて窓を閉めると、朝の5時。ああ、幸せ、あと30分眠れる、と布団にもぐりこむ。布団のなかでうつらうつらとする朝の30分は、至福のときである。デジタル時計に表示された気温を見ると23℃。前夜の雨のせいか、涼しく気持ちのいい朝だ。
そんな布団なのかで、ふわふわとした気分のまま、耳に入って来たのはウグイスの鳴き声だった。ホーホケキョ。春の頃、たどたどしく鳴いていた声とは違い、しっかりとした自信を感じる、透明感のある美しい声だ。
「夏にも、ウグイスはいるんだなあ」
ぼんやりと考えた。ウグイスは春の鳥というイメージが強すぎて、まるで春にだけ現れ、すっと消えていくかのように思っていた。しかし、幻の野鳥という訳ではないのだから、当然どの季節にも何処かにいるはずだ。野鳥図鑑で調べれば、寒冷地では暖地に移ることはあっても、1年中一所に住むウグイスも多いらしい。ホーホケキョと鳴く時期が、春から夏なのだった。
見えない部分、見ようとしていない部分、知らない部分は、まるで「ない」ように思いがちだ。だがウグイスは、いつもいつでも何処かにいるのだ。

八ヶ岳を覆うように湧き出ていた、夏らしい雲達。

こちらは、南アルプスは甲斐駒ケ岳にかかった雲の様子です。
じつは、ウグイス、目撃したことはありません。

寒い、と感じて窓を閉めると、朝の5時。ああ、幸せ、あと30分眠れる、と布団にもぐりこむ。布団のなかでうつらうつらとする朝の30分は、至福のときである。デジタル時計に表示された気温を見ると23℃。前夜の雨のせいか、涼しく気持ちのいい朝だ。
そんな布団なのかで、ふわふわとした気分のまま、耳に入って来たのはウグイスの鳴き声だった。ホーホケキョ。春の頃、たどたどしく鳴いていた声とは違い、しっかりとした自信を感じる、透明感のある美しい声だ。
「夏にも、ウグイスはいるんだなあ」
ぼんやりと考えた。ウグイスは春の鳥というイメージが強すぎて、まるで春にだけ現れ、すっと消えていくかのように思っていた。しかし、幻の野鳥という訳ではないのだから、当然どの季節にも何処かにいるはずだ。野鳥図鑑で調べれば、寒冷地では暖地に移ることはあっても、1年中一所に住むウグイスも多いらしい。ホーホケキョと鳴く時期が、春から夏なのだった。
見えない部分、見ようとしていない部分、知らない部分は、まるで「ない」ように思いがちだ。だがウグイスは、いつもいつでも何処かにいるのだ。
八ヶ岳を覆うように湧き出ていた、夏らしい雲達。
こちらは、南アルプスは甲斐駒ケ岳にかかった雲の様子です。
じつは、ウグイス、目撃したことはありません。
ラーメン、ラララ
所用で甲府に出た際、久しぶりにラーメンを食べた。
このところの暑さで、夫との昼食でラーメンを食べようという話にならない。わたしとしては、ラーメン食べたいなあと思っていても、夫の「この暑いのにラーメン?」のひと言であきらめていたのだ。だから、久々に食べようと、朝から決めて、わくわくしていた。
がんがんに冷房が効いたラーメン屋で、熱々の辛葱ラーメンを食べる。幸せだ。何が幸せかって、葱がさらし過ぎていないのが、いい。ラーメン屋のさらし過ぎた葱ほど許せないものはない。自然な葱の辛さを味わいつつ、すするラーメン。ラーメン、ラララと歌いたくなるほど美味かった。
さて。その帰り、スーパーで買い物をした。誰も並んでいないレジにカゴを置くと、何かのトラブルか、商品を替えに行っていた客が戻って来た。レジの女性が申し訳なさそうに「お先に、この方、いいですか?」と聞く。「どうぞ」と先を譲ると、その客も「すみません」と頭を下げた。普段なら、そこで笑顔で会釈するくらいだったと思うが、ラーメン、ラララだったわたしは、機嫌よくはきはきと言った。「いいですよ。だいじょうぶです」ふたりとも、ぱっと笑顔になる。それを見て、わたしも笑顔になった。
その後わたしの番になると、レジの女性は、本当はダメなんだけどという顔で「それ、マイバックですか? 入れましょうか」と言った。そこのスーパーのルールでは、カゴ相当の大きさのマイバッグにしか、レジ担当者は商品を入れないことになっている。レジをスムーズにという理由からだ。わたしは後ろに誰も並んでいないことを確認し「じゃ、お願いします」と甘えることにした。
なんだかすごくいい気分だった。たぶん、前の客も、レジにいた女性も、同じようにいい気分だったと思うから余計に。
これからは、ラーメン、ラララじゃなくっても、きちんと言葉で伝えよう。
なあんて思ったのも、ラーメンの美味しさによるご機嫌な連鎖かな。うーん。ラーメンは偉大だ。

辛葱ラーメンの麺かため、醤油うすめ、脂少なめにしました。

東京豚骨拉麺ばんからラーメンのモットーは『胸はって、見栄はらず』

このところの暑さで、夫との昼食でラーメンを食べようという話にならない。わたしとしては、ラーメン食べたいなあと思っていても、夫の「この暑いのにラーメン?」のひと言であきらめていたのだ。だから、久々に食べようと、朝から決めて、わくわくしていた。
がんがんに冷房が効いたラーメン屋で、熱々の辛葱ラーメンを食べる。幸せだ。何が幸せかって、葱がさらし過ぎていないのが、いい。ラーメン屋のさらし過ぎた葱ほど許せないものはない。自然な葱の辛さを味わいつつ、すするラーメン。ラーメン、ラララと歌いたくなるほど美味かった。
さて。その帰り、スーパーで買い物をした。誰も並んでいないレジにカゴを置くと、何かのトラブルか、商品を替えに行っていた客が戻って来た。レジの女性が申し訳なさそうに「お先に、この方、いいですか?」と聞く。「どうぞ」と先を譲ると、その客も「すみません」と頭を下げた。普段なら、そこで笑顔で会釈するくらいだったと思うが、ラーメン、ラララだったわたしは、機嫌よくはきはきと言った。「いいですよ。だいじょうぶです」ふたりとも、ぱっと笑顔になる。それを見て、わたしも笑顔になった。
その後わたしの番になると、レジの女性は、本当はダメなんだけどという顔で「それ、マイバックですか? 入れましょうか」と言った。そこのスーパーのルールでは、カゴ相当の大きさのマイバッグにしか、レジ担当者は商品を入れないことになっている。レジをスムーズにという理由からだ。わたしは後ろに誰も並んでいないことを確認し「じゃ、お願いします」と甘えることにした。
なんだかすごくいい気分だった。たぶん、前の客も、レジにいた女性も、同じようにいい気分だったと思うから余計に。
これからは、ラーメン、ラララじゃなくっても、きちんと言葉で伝えよう。
なあんて思ったのも、ラーメンの美味しさによるご機嫌な連鎖かな。うーん。ラーメンは偉大だ。
辛葱ラーメンの麺かため、醤油うすめ、脂少なめにしました。
東京豚骨拉麺ばんからラーメンのモットーは『胸はって、見栄はらず』
夢の歪み
夢を見た。おむすびを食べようと、海苔を出したのだが、その海苔が変に細長いのだ。どうして? と戸惑っている自分が、夢のなかにいた。
このところ、よくおむすびを食べる。朝食に炊いたご飯の残りをむすび、冷蔵庫に入れておき、昼食に、ひとりの夕食にレンジでチンして海苔を巻く。お茶碗によそったご飯よりも食欲が湧くのだ。そんな日々のなか、見た夢だった。
考えるに、海苔って微妙に長方形だよなあという疑問が、わたしのなかにはあったのだと思う。どうして正方形じゃあ駄目なんだろう、という疑問が。
それが夢のなかで誇張され、はっきりとした長方形の海苔が出来上がったというのが推測だ。
そんな小さな日常の歪みが、夢に出てくることがよくある。
庭仕事をした夫のポロシャツの汚れが取れず、洗い直そうと洗濯機の上に置いたまま忘れていた。ここまでは現実。ここからが夢なのだが、夫がそのポロシャツをタオルにして顔を洗っているのだ。
「あ、それ、ポロシャツだから」
戸惑うわたし。ただそれだけの夢だが、忘れていたポロシャツを何処かで覚えていた自分がいて、夢を見た訳だ。思考回路が単純だとも言える。
しかしまあ、気になることを夢に見るというのなら、まるで悩みがないようだな、わたし。と客観視し、冷静に考えたのだった。

玄米入りの少し茶色っぽい、おむすびです。熱中症予防に梅干し!
海苔の大きさは21㎝ × 19㎝ に、昭和40年代に統一されたそうです。
何故かは、わかりませんでした。

お米は、近所の田んぼのおばあちゃんから買っています。
今年も、稲がすくすく育っていく様子が見られて、うれしいです。

このところ、よくおむすびを食べる。朝食に炊いたご飯の残りをむすび、冷蔵庫に入れておき、昼食に、ひとりの夕食にレンジでチンして海苔を巻く。お茶碗によそったご飯よりも食欲が湧くのだ。そんな日々のなか、見た夢だった。
考えるに、海苔って微妙に長方形だよなあという疑問が、わたしのなかにはあったのだと思う。どうして正方形じゃあ駄目なんだろう、という疑問が。
それが夢のなかで誇張され、はっきりとした長方形の海苔が出来上がったというのが推測だ。
そんな小さな日常の歪みが、夢に出てくることがよくある。
庭仕事をした夫のポロシャツの汚れが取れず、洗い直そうと洗濯機の上に置いたまま忘れていた。ここまでは現実。ここからが夢なのだが、夫がそのポロシャツをタオルにして顔を洗っているのだ。
「あ、それ、ポロシャツだから」
戸惑うわたし。ただそれだけの夢だが、忘れていたポロシャツを何処かで覚えていた自分がいて、夢を見た訳だ。思考回路が単純だとも言える。
しかしまあ、気になることを夢に見るというのなら、まるで悩みがないようだな、わたし。と客観視し、冷静に考えたのだった。
玄米入りの少し茶色っぽい、おむすびです。熱中症予防に梅干し!
海苔の大きさは21㎝ × 19㎝ に、昭和40年代に統一されたそうです。
何故かは、わかりませんでした。
お米は、近所の田んぼのおばあちゃんから買っています。
今年も、稲がすくすく育っていく様子が見られて、うれしいです。
『天使はモップを持って』
引き続き、近藤史恵を読んでいる。『天使はモップを持って』(文春文庫)
オフィスを舞台にしたミステリー要素たっぷりの連作短編集だ。
変わっているのは、探偵役をするビルの掃除を仕事にする人物が、モップなど似合わないようなファッショナブルな格好をした十代の女の子だということだ。彼女はキリコ。主人公はそのビルの会社に入社したばかりの大介だ。
そんなキリコと大介が、社内で起こった謎を解いていく。キリコが掃除する場所には、意識せずとも謎解きのヒントが隠されている。ゴミを捨てる人も、汚す人も、そこを掃除する人間がどう思うかなど考えることはない。翌朝、オフィスが綺麗になっていてもそれは当然のことであり、掃除をする人が入ったのだと想像力を働かせる人は少ない。キリコが掃除する場所には常に人の心の隙や油断が落ちていて、そこから人の本性が見え隠れもする場所なのである。
謎が解けたことで、そんな人の心根を垣間見てしまい、人間関係の修復に悩む大介に、キリコは言う。以下本文から。
「大丈夫、世の中はお掃除と一緒だよ。汚れたらきれいにすればいい。また、汚れちゃうかもしれないけど、また、きれいにすればいい」
「でも、絶対、落ちない汚れだってあるだろう」
「そりゃあ、ね。でも大部分は、根気とテクニックさえあれば、なんとかなっちゃうもんよ。コツとしては早いほど落ちやすいってこともあるけどね」
掃除の仕事に誇りを持って、毎日を過ごしているキリコは、本当に眩しい。

カラフルな表紙のキリコ、とっても可愛いです。
続編『モップの精は深夜に現れる』も、おもしろかった!

オフィスを舞台にしたミステリー要素たっぷりの連作短編集だ。
変わっているのは、探偵役をするビルの掃除を仕事にする人物が、モップなど似合わないようなファッショナブルな格好をした十代の女の子だということだ。彼女はキリコ。主人公はそのビルの会社に入社したばかりの大介だ。
そんなキリコと大介が、社内で起こった謎を解いていく。キリコが掃除する場所には、意識せずとも謎解きのヒントが隠されている。ゴミを捨てる人も、汚す人も、そこを掃除する人間がどう思うかなど考えることはない。翌朝、オフィスが綺麗になっていてもそれは当然のことであり、掃除をする人が入ったのだと想像力を働かせる人は少ない。キリコが掃除する場所には常に人の心の隙や油断が落ちていて、そこから人の本性が見え隠れもする場所なのである。
謎が解けたことで、そんな人の心根を垣間見てしまい、人間関係の修復に悩む大介に、キリコは言う。以下本文から。
「大丈夫、世の中はお掃除と一緒だよ。汚れたらきれいにすればいい。また、汚れちゃうかもしれないけど、また、きれいにすればいい」
「でも、絶対、落ちない汚れだってあるだろう」
「そりゃあ、ね。でも大部分は、根気とテクニックさえあれば、なんとかなっちゃうもんよ。コツとしては早いほど落ちやすいってこともあるけどね」
掃除の仕事に誇りを持って、毎日を過ごしているキリコは、本当に眩しい。
カラフルな表紙のキリコ、とっても可愛いです。
続編『モップの精は深夜に現れる』も、おもしろかった!
説明する人と、それを聞く人
週末、この夏初めて室内温度が30℃を越えた。エアコンがなくても過ごせていた夏は、何処へ行ったのか。
「涼しい場所まで、登ろうか」
夫の提案で、標高の高い方へとドライブすることにした。
「何処に行く?」「ノーアイディア」
やる気なく、だらだらとしたドライブだ。なんとなく北杜市も長野寄りに向かううち、県境の先、野辺山辺りなら涼しいだろうと、目指すことになった。
野辺山駅は、日本一標高の高いJRの駅だ。1345mある。走っていると、大きなパラボラアンテナのようなものが見えた。道標に『国立天文台・野辺山宇宙電波観測所』とある。行ってみることにした。
入場無料で自由に見学ができる、その広々とした場所には、ボーイスカウトの集団やら家族連れやらカップルやら、見学者がけっこういた。
陽が当たる場所は暑かったが、日陰は涼しかった。
「宇宙人って、やっぱり頭が大きな二頭身タイプ、思い浮かべるよね」
わたしが思いついたままに言うと、夫に冷たい目で返された。
「ここには宇宙人、いないから。宇宙からの電波を観測する場所なんだから」
「そうなの? いないんだー、なあんだ」
暑さにやられ、すでにわたしの思考回路は壊れてしまっていた。だが、前を歩くカップルを見ると、男性が女性に熱心に説明している。
「天体から放出される電波は、とても弱いんだ。だから、人工の電波が少なくて標高の高い野辺山で研究されているんだよ」
すれ違った親子も、父親と思われる人が小学生らしき息子くんに説明していた。女性同士の二人連れも片方が片方に、やはり熱心に話している。
「説明する人と、それを聞く人がいるんだな」
思考回路が回らないまま、ぼんやりと考える。そのとき、足もとに白線が見えた。長く道の先まで続いている。いちばん大きな電波望遠鏡の直径と同じ長さ、45mとかかれていた。
「電波望遠鏡の直径の長さは、このくらいあるんだよ」
足もとの白線を指さし、珍しく、夫に説明する。
「本当だ。気づかなかった。きみは、いろいろなところを見ているんだね」
えへん。と胸を張ったわたしは、じつは陽の光が眩しくて、足もとのみを見つめて歩いていたのだが、たまには説明する側に立つのも気持ちがいいものだなあと、少しだけ涼しい野辺山を、機嫌よく歩いたのだった。

こちらは、6台ある直径10mのミリ波干渉計です。

これが、世界最大級のミリ波干渉計、直径45mの電波望遠鏡です。

「涼しい場所まで、登ろうか」
夫の提案で、標高の高い方へとドライブすることにした。
「何処に行く?」「ノーアイディア」
やる気なく、だらだらとしたドライブだ。なんとなく北杜市も長野寄りに向かううち、県境の先、野辺山辺りなら涼しいだろうと、目指すことになった。
野辺山駅は、日本一標高の高いJRの駅だ。1345mある。走っていると、大きなパラボラアンテナのようなものが見えた。道標に『国立天文台・野辺山宇宙電波観測所』とある。行ってみることにした。
入場無料で自由に見学ができる、その広々とした場所には、ボーイスカウトの集団やら家族連れやらカップルやら、見学者がけっこういた。
陽が当たる場所は暑かったが、日陰は涼しかった。
「宇宙人って、やっぱり頭が大きな二頭身タイプ、思い浮かべるよね」
わたしが思いついたままに言うと、夫に冷たい目で返された。
「ここには宇宙人、いないから。宇宙からの電波を観測する場所なんだから」
「そうなの? いないんだー、なあんだ」
暑さにやられ、すでにわたしの思考回路は壊れてしまっていた。だが、前を歩くカップルを見ると、男性が女性に熱心に説明している。
「天体から放出される電波は、とても弱いんだ。だから、人工の電波が少なくて標高の高い野辺山で研究されているんだよ」
すれ違った親子も、父親と思われる人が小学生らしき息子くんに説明していた。女性同士の二人連れも片方が片方に、やはり熱心に話している。
「説明する人と、それを聞く人がいるんだな」
思考回路が回らないまま、ぼんやりと考える。そのとき、足もとに白線が見えた。長く道の先まで続いている。いちばん大きな電波望遠鏡の直径と同じ長さ、45mとかかれていた。
「電波望遠鏡の直径の長さは、このくらいあるんだよ」
足もとの白線を指さし、珍しく、夫に説明する。
「本当だ。気づかなかった。きみは、いろいろなところを見ているんだね」
えへん。と胸を張ったわたしは、じつは陽の光が眩しくて、足もとのみを見つめて歩いていたのだが、たまには説明する側に立つのも気持ちがいいものだなあと、少しだけ涼しい野辺山を、機嫌よく歩いたのだった。
こちらは、6台ある直径10mのミリ波干渉計です。
これが、世界最大級のミリ波干渉計、直径45mの電波望遠鏡です。
茗荷と物忘れ
庭の茗荷が、花を咲かせた。嬉しい。待っていたのである。
茗荷達が、頭をのぞかせているのは知っていた。だが、収穫するにはまだやせっぽちだ。お菓子の家の人食い魔女よろしく、太れ太れと唱えながら、花が咲くのを今か今かと待ちわびていた。ようやくその時が来たのだ。
「茗荷の味が、濃いねえ」
朝食の味噌汁をすすり、夫がうなずきつつ言う。確かに、味が濃い。小松菜とシメジの味噌汁だったが、たっぷり入れた薬味である茗荷の主張が強く、茗荷汁と言ってもいいような味わいになってしまった。
春からこちら、毎朝の味噌汁の薬味は茗荷と決めて、収穫できずにいる間も買って来て入れていたが、やはり獲れたては違う。
茗荷を収穫し、そう言えば、と思い出した。「茗荷を食べると物忘れをする」という諺である。だが毎日、茗荷を食べていて、最近とみに物忘れがひどくなったかと言えば、そうでもない。というのは、もうずいぶんと前から、十年以上前だろうか、物忘れがひどいなあと感じてから、たいして変わらないような気がしていたのだ。しかし、茗荷の諺をすっかり忘れていたことには、ショックを受けた。物忘れを物忘れとも思わぬほど、進行していたのだろうか。いやしかし「灯台下暗し」という諺もある。それだけ茗荷が生活のなかで身近な存在になったという証かも知れない。
ということで、茗荷を食べすぎたがために物忘れが進行したという説は忘れることにして、これからしばらく庭の茗荷を美味しく楽しくいただこうと思う。

花を咲かせた茗荷達。順番に収穫するから、待っててね。

収穫した茗荷です。美しいです。

茗荷の味噌汁には、花も入れました。
家庭菜園で作ったといただいた野菜や、もずく、納豆と一緒に、朝ご飯。

茗荷達が、頭をのぞかせているのは知っていた。だが、収穫するにはまだやせっぽちだ。お菓子の家の人食い魔女よろしく、太れ太れと唱えながら、花が咲くのを今か今かと待ちわびていた。ようやくその時が来たのだ。
「茗荷の味が、濃いねえ」
朝食の味噌汁をすすり、夫がうなずきつつ言う。確かに、味が濃い。小松菜とシメジの味噌汁だったが、たっぷり入れた薬味である茗荷の主張が強く、茗荷汁と言ってもいいような味わいになってしまった。
春からこちら、毎朝の味噌汁の薬味は茗荷と決めて、収穫できずにいる間も買って来て入れていたが、やはり獲れたては違う。
茗荷を収穫し、そう言えば、と思い出した。「茗荷を食べると物忘れをする」という諺である。だが毎日、茗荷を食べていて、最近とみに物忘れがひどくなったかと言えば、そうでもない。というのは、もうずいぶんと前から、十年以上前だろうか、物忘れがひどいなあと感じてから、たいして変わらないような気がしていたのだ。しかし、茗荷の諺をすっかり忘れていたことには、ショックを受けた。物忘れを物忘れとも思わぬほど、進行していたのだろうか。いやしかし「灯台下暗し」という諺もある。それだけ茗荷が生活のなかで身近な存在になったという証かも知れない。
ということで、茗荷を食べすぎたがために物忘れが進行したという説は忘れることにして、これからしばらく庭の茗荷を美味しく楽しくいただこうと思う。
花を咲かせた茗荷達。順番に収穫するから、待っててね。
収穫した茗荷です。美しいです。
茗荷の味噌汁には、花も入れました。
家庭菜園で作ったといただいた野菜や、もずく、納豆と一緒に、朝ご飯。
桔梗の濃い紫色
桔梗の花が、好きだ。濃い紫色。その色にとても魅かれる。
何色が好き? などというクエスチョンには「迷うなあ」と優柔不断さいっぱいで答えられないし、白も黒も、赤も青も黄色も、それぞれ好きだったりする。それでも紫に特別心魅かれるものがあるのは否定できない。
何故だろうと考えて、紫は、赤と青をブレンドした色だったと、子どもの頃に絵の具を混ぜたことを思い出した。そしてさらに『冷静と情熱の間』(角川書店)という青と赤の二冊の小説を思い出す。女性視点を江國香織が、男性視点を辻仁成が、交互にかいていった合作の恋愛小説だ。
冷静からは青い色を、情熱からは赤い色を連想する。紫は、そんな二面性を持つ色なのだ。静と動、という相反するものを持つ色とも言える。
自分でもままならない、自分のなかの相反するものを知らず知らずに感じとり、訳もなく桔梗の紫に魅かれるのかも知れない、と考えてみる。
今、庭には桔梗が、毎日のように新しい花を咲かせている。

庭の桔梗です。強い陽射しのなか、風に揺れていました。

こちらは、紫式部の花。緑色の実が、根元の方からできてきています。
花よりも実の方が、濃いめの紫に色づいていきます。

様々な種類の蝉の抜け殻が、あちらこちらに点在中。

蕗の葉の上にはけろじが。影に入りこんでいました。

何色が好き? などというクエスチョンには「迷うなあ」と優柔不断さいっぱいで答えられないし、白も黒も、赤も青も黄色も、それぞれ好きだったりする。それでも紫に特別心魅かれるものがあるのは否定できない。
何故だろうと考えて、紫は、赤と青をブレンドした色だったと、子どもの頃に絵の具を混ぜたことを思い出した。そしてさらに『冷静と情熱の間』(角川書店)という青と赤の二冊の小説を思い出す。女性視点を江國香織が、男性視点を辻仁成が、交互にかいていった合作の恋愛小説だ。
冷静からは青い色を、情熱からは赤い色を連想する。紫は、そんな二面性を持つ色なのだ。静と動、という相反するものを持つ色とも言える。
自分でもままならない、自分のなかの相反するものを知らず知らずに感じとり、訳もなく桔梗の紫に魅かれるのかも知れない、と考えてみる。
今、庭には桔梗が、毎日のように新しい花を咲かせている。
庭の桔梗です。強い陽射しのなか、風に揺れていました。
こちらは、紫式部の花。緑色の実が、根元の方からできてきています。
花よりも実の方が、濃いめの紫に色づいていきます。
様々な種類の蝉の抜け殻が、あちらこちらに点在中。
蕗の葉の上にはけろじが。影に入りこんでいました。
『ダークルーム』
近藤史恵の短編集『ダークルーム』(角川文庫)を、読んだ。
8編のミステリーは、裏表紙で、こう紹介されている。
「立ちはだかる現実に絶望し、窮地に立たされた人間たちが取った異常な行動とは。日常に潜む狂気と、明かされる驚愕の真相」
高級フレンチレストランで、毎晩ひとり食事する美女。自殺した元恋人が、新しい恋人に乗り移ったと疑う男。双子の美少女モデル達と、殺されたマネージャー。何も知らないふりをしつつ、兄の恋人に激しい嫉妬を抱く妹。
ひとつひとつのストーリーが、静かな寒気を呼ぶ恐ろしさを持っていた。
なかでも、いちばん好きだったのはラストに収められた書き下ろし『北緯六十度の恋』だ。多佳子は恋人の園子とフィンランドを訪れた。3年前から同性愛者の園子の恋人として振舞ってきた多佳子には、園子への復讐の計画があった。以下本文から。
草というのを聞いたことがあるだろうか。
わたしは子供の頃、弟の部屋でこっそり読んだ忍者漫画で知った。
草の任務についた忍者は、その標的の土地に普通の人として移り住む。そして三年、五年、ときによっては何十年も忍者としての自分を隠して、そこで生活を営むのだ。そして、すっかりそこに溶け込んだ頃に、任務遂行の知らせがやってくる。それが暗殺や、重要な情報を雇い主に流すことだったとしても、すっかりその土地やコミュニティに溶け込んでしまった草は疑われない。簡単に敵の懐に忍び込み、任務を遂行することができるのだ。
多佳子は、共に3年の月日を過ごし、手酷い裏切りで園子の傷が深くなることを確信し、計画を実行しようとしていた。だが、その先に待っていたものは。
もし何年も信頼し合ってきたと思える人が「草」と同じことをしようとしていたら? そう考えると空恐ろしくなるが、また逆に、人は、人を信頼することで生きているのだと、本を閉じ、強く思ったのだった。

カフェラテを飲みながら、読書タイム。夏に合う涼しくなる小説です。

8編のミステリーは、裏表紙で、こう紹介されている。
「立ちはだかる現実に絶望し、窮地に立たされた人間たちが取った異常な行動とは。日常に潜む狂気と、明かされる驚愕の真相」
高級フレンチレストランで、毎晩ひとり食事する美女。自殺した元恋人が、新しい恋人に乗り移ったと疑う男。双子の美少女モデル達と、殺されたマネージャー。何も知らないふりをしつつ、兄の恋人に激しい嫉妬を抱く妹。
ひとつひとつのストーリーが、静かな寒気を呼ぶ恐ろしさを持っていた。
なかでも、いちばん好きだったのはラストに収められた書き下ろし『北緯六十度の恋』だ。多佳子は恋人の園子とフィンランドを訪れた。3年前から同性愛者の園子の恋人として振舞ってきた多佳子には、園子への復讐の計画があった。以下本文から。
草というのを聞いたことがあるだろうか。
わたしは子供の頃、弟の部屋でこっそり読んだ忍者漫画で知った。
草の任務についた忍者は、その標的の土地に普通の人として移り住む。そして三年、五年、ときによっては何十年も忍者としての自分を隠して、そこで生活を営むのだ。そして、すっかりそこに溶け込んだ頃に、任務遂行の知らせがやってくる。それが暗殺や、重要な情報を雇い主に流すことだったとしても、すっかりその土地やコミュニティに溶け込んでしまった草は疑われない。簡単に敵の懐に忍び込み、任務を遂行することができるのだ。
多佳子は、共に3年の月日を過ごし、手酷い裏切りで園子の傷が深くなることを確信し、計画を実行しようとしていた。だが、その先に待っていたものは。
もし何年も信頼し合ってきたと思える人が「草」と同じことをしようとしていたら? そう考えると空恐ろしくなるが、また逆に、人は、人を信頼することで生きているのだと、本を閉じ、強く思ったのだった。
カフェラテを飲みながら、読書タイム。夏に合う涼しくなる小説です。
きらきら輝いてる夏ですか?
「毎日楽しいこと、きらきら輝いてる夏ですか?」
東京に住む友人から、メールをもらった。正月明けに貿易センタービルの展望室で、缶ビールを飲みながら弁当を食べて以来だから、半年ぶりである。
そのメールを読み、ハッとした。毎日、ただただ暑いよなあと、きらきらどころか、ぐだぐだと過ごしていたのだ。
下を向いて黙々と歩いているときに、空が青くて眩しいよ、と、ぽんと肩をたたかれたような気分だった。歩くことに夢中になるがあまり、足もとしか見られなくなっているとき、というのが、生きていればままあるものだ。
その友人が、昨日、息子くんと訪ねてきてくれた。短い時間だったが、ゆったりとおしゃべりをし、一緒に明野名物の向日葵畑を観に行った。
顔を上げ、見た夏は、きらきらと輝いていた。

明野向日葵『サンフラワーフェス』開催中です。

東京に住む友人から、メールをもらった。正月明けに貿易センタービルの展望室で、缶ビールを飲みながら弁当を食べて以来だから、半年ぶりである。
そのメールを読み、ハッとした。毎日、ただただ暑いよなあと、きらきらどころか、ぐだぐだと過ごしていたのだ。
下を向いて黙々と歩いているときに、空が青くて眩しいよ、と、ぽんと肩をたたかれたような気分だった。歩くことに夢中になるがあまり、足もとしか見られなくなっているとき、というのが、生きていればままあるものだ。
その友人が、昨日、息子くんと訪ねてきてくれた。短い時間だったが、ゆったりとおしゃべりをし、一緒に明野名物の向日葵畑を観に行った。
顔を上げ、見た夏は、きらきらと輝いていた。
明野向日葵『サンフラワーフェス』開催中です。
『六番目の小夜子』
ずっと読みたいと思いつつ開くことのなかった恩田陸デビュー作『六番目の小夜子』(新潮文庫)を、読んだ。いやー、おもしろかった。
事前情報は何も見ずに読み始め、タイトルと表紙から学園モノのホラーかと思い込んでいたせいか、何処で人が死ぬ? 何処で怖いシーンが? と緊張してもいたのだが、ホラーではなかった。100%ホラーじゃないと言い切る自信はないのだが。
舞台は地方の高校。進学校であるその高校には、奇妙な言い伝えが受け継がれていた。卒業していく「サヨコ」に鍵を渡された生徒が次の「サヨコ」になる、というものだ。「サヨコ」は三年ごとに行動を起こさなくてはならない。ストーリーは、行動を起こすべき「サヨコ」が、六番目の年の物語だ。そこへ、沙世子という名の美しく謎めいた転校生がやってきた。
読み終えて感じたのは、学校という場所の不思議さだった。以下本文から。
溢れる学生服とセーラー服に、雅子は圧倒されそうになる。
黒と紺の塊が、くっつき、離れ、思い思いのエネルギーを放射している。それでいて、塊全体が一つの意思を持ち、うごめいているかのようだ。学校というのは、なんて変なところなのだろう。同じ歳の男の子と女の子がこんなにたくさん集まって、あの狭く四角い部屋にずらりと机を並べているなんて。なんと特異で、なんと優遇された、そしてなんと閉じられた空間なのだろう。
学校という入れ物のなかには、そこを通り過ぎていく生徒達だからこそ生まれる一体感があり、小説はその閉鎖された場所での一体感が起こす不思議を描いていた。この小説を読み、学校の怪談などが生まれるのも、やはりその「閉鎖された場所での一体感」から来るのではないかと、腑に落ちた。
読後、様々なレビューを読むと、張りめぐらされた伏線が回収されていない、最後までよく判らないとの意見が多く見られた。だが、わたしは学校という場所が起こす不思議を垣間見ることができ、満ち足りた気分で本を閉じたのだ。

赤に、無表情なセーラー服の女生徒が印象的な表紙です。

事前情報は何も見ずに読み始め、タイトルと表紙から学園モノのホラーかと思い込んでいたせいか、何処で人が死ぬ? 何処で怖いシーンが? と緊張してもいたのだが、ホラーではなかった。100%ホラーじゃないと言い切る自信はないのだが。
舞台は地方の高校。進学校であるその高校には、奇妙な言い伝えが受け継がれていた。卒業していく「サヨコ」に鍵を渡された生徒が次の「サヨコ」になる、というものだ。「サヨコ」は三年ごとに行動を起こさなくてはならない。ストーリーは、行動を起こすべき「サヨコ」が、六番目の年の物語だ。そこへ、沙世子という名の美しく謎めいた転校生がやってきた。
読み終えて感じたのは、学校という場所の不思議さだった。以下本文から。
溢れる学生服とセーラー服に、雅子は圧倒されそうになる。
黒と紺の塊が、くっつき、離れ、思い思いのエネルギーを放射している。それでいて、塊全体が一つの意思を持ち、うごめいているかのようだ。学校というのは、なんて変なところなのだろう。同じ歳の男の子と女の子がこんなにたくさん集まって、あの狭く四角い部屋にずらりと机を並べているなんて。なんと特異で、なんと優遇された、そしてなんと閉じられた空間なのだろう。
学校という入れ物のなかには、そこを通り過ぎていく生徒達だからこそ生まれる一体感があり、小説はその閉鎖された場所での一体感が起こす不思議を描いていた。この小説を読み、学校の怪談などが生まれるのも、やはりその「閉鎖された場所での一体感」から来るのではないかと、腑に落ちた。
読後、様々なレビューを読むと、張りめぐらされた伏線が回収されていない、最後までよく判らないとの意見が多く見られた。だが、わたしは学校という場所が起こす不思議を垣間見ることができ、満ち足りた気分で本を閉じたのだ。
赤に、無表情なセーラー服の女生徒が印象的な表紙です。
新しいノート
本棚を物色していたら、新しノートが出てきた。買ったまま、仕舞いこんでいたらしい。カエルが表紙にかかれた、なかは無地のノートだ。
そのカエルを見て「おお!」と思わずつぶやく。気に入って購入したことを思い出したのだ。それなのに、使いもせず忘れてしまうとは。
さっそく開き、何に使おうか考えた。真っ白いノートは、いい。何かが新しく始まる予感がする。あれこれ考えるだけで、楽しくなる。
そのとき、外でパラパラと音がした。夕立ちだ。ザーッときた。
「きみ、鳴いた?」
ノートのカエルに声をかける。本棚から出られて、よほどうれしかったのだろう。湿った空気に、気持ちよさそうにしていた。

表紙のカエルくん、水かきの辺りのリアルさがいい感じです。

薪置場の波板が木陰になっていて、そこで涼んでいたけろじ。
このあと跳ねて反転しました。その姿は上の絵のように手足が長かった。

そのカエルを見て「おお!」と思わずつぶやく。気に入って購入したことを思い出したのだ。それなのに、使いもせず忘れてしまうとは。
さっそく開き、何に使おうか考えた。真っ白いノートは、いい。何かが新しく始まる予感がする。あれこれ考えるだけで、楽しくなる。
そのとき、外でパラパラと音がした。夕立ちだ。ザーッときた。
「きみ、鳴いた?」
ノートのカエルに声をかける。本棚から出られて、よほどうれしかったのだろう。湿った空気に、気持ちよさそうにしていた。
表紙のカエルくん、水かきの辺りのリアルさがいい感じです。
薪置場の波板が木陰になっていて、そこで涼んでいたけろじ。
このあと跳ねて反転しました。その姿は上の絵のように手足が長かった。
蕎麦屋の待ち時間
週末、食材の買い出しがてら、夫と蕎麦屋に行った。
ここ北杜市には蕎麦屋が多く、まだ行ったことのない店もたくさんあるが、そこはずいぶん前にやはり買い物がてら食べに寄った店で、スーパーに行く途中、通り道にある。『やつこま』という蕎麦屋だ。
日曜で天気も良く、店は混んでいた。急ぐ必要は何もないので夫とふたりゆっくりと待つ。通された窓際の席からは、まだ咲いていない向日葵畑と「標高700m」の看板が見え、風が通って気持ちがよかった。店が二階なので見下ろす感じだ。
運転は任せて、と夫にビールをすすめ、蕎麦の到着を待つ。その間、ほとんど何もしゃべらなかった。ビールのグラスが木製で、その木の器がよく冷えていたことに感心し、ひと言ふた言話したくらいだ。テーブルは5つほど。みながのんびりとした心持ちでいるように見えた。
何事もない時間だった。単なる待ち時間なのだが、急く気持ちもなく、日々の細かな悩み事も忘れ、まるで時間が止まっているかのように感じた。透明な時間だ、と思った。いつでも手に入るような、それでいていつもはするりと逃げてしまい捕まえられない、そんな時間がここにある、と感じた。
蕎麦は美味かった。
「こんなに美味い蕎麦は、ここ最近食べてない」
夫も絶賛だった。音をたてて蕎麦をすすり、止まっていた時間が流れ出した。

平打ちの麺は、強いコシがありました。きのこと野菜の天麩羅と。

ここ北杜市には蕎麦屋が多く、まだ行ったことのない店もたくさんあるが、そこはずいぶん前にやはり買い物がてら食べに寄った店で、スーパーに行く途中、通り道にある。『やつこま』という蕎麦屋だ。
日曜で天気も良く、店は混んでいた。急ぐ必要は何もないので夫とふたりゆっくりと待つ。通された窓際の席からは、まだ咲いていない向日葵畑と「標高700m」の看板が見え、風が通って気持ちがよかった。店が二階なので見下ろす感じだ。
運転は任せて、と夫にビールをすすめ、蕎麦の到着を待つ。その間、ほとんど何もしゃべらなかった。ビールのグラスが木製で、その木の器がよく冷えていたことに感心し、ひと言ふた言話したくらいだ。テーブルは5つほど。みながのんびりとした心持ちでいるように見えた。
何事もない時間だった。単なる待ち時間なのだが、急く気持ちもなく、日々の細かな悩み事も忘れ、まるで時間が止まっているかのように感じた。透明な時間だ、と思った。いつでも手に入るような、それでいていつもはするりと逃げてしまい捕まえられない、そんな時間がここにある、と感じた。
蕎麦は美味かった。
「こんなに美味い蕎麦は、ここ最近食べてない」
夫も絶賛だった。音をたてて蕎麦をすすり、止まっていた時間が流れ出した。
平打ちの麺は、強いコシがありました。きのこと野菜の天麩羅と。
ハマナスの実
庭のハマナスの実が色づいてきたので、収穫した。
バラ科のハマナスの実は、ローズヒップとも呼ばれ、栄養価が高いらしい。
生でも食べられるというのでさっそく洗ってかじってみる。
「わ、種だらけ」
酸味と一緒に広がったのは、種の食感。失敗した。新しいものを半分に切ってみると、実の中身は種の部分が大半をしめている。その種部分をとってから、皮についた実の部分を食べるべきだったのだ。生で食べられると調べて安心し、油断したのであった。
こういう失敗が、子どもの頃からよくある。
両親の田舎である北海道で、木彫りの人形などを売る店に繋がれていた子熊に引っ掻かれたのも、わたしだけだった。
「可愛い!」と、つい手を出し、がりっとやられたのだ。今考えるに恐ろしいが、熊は絵本などに登場する可愛らしいものという認識だったのだろう。同じようにして、ペットショップで子猿にも引っ掻かれているから、学習しないと言うか何と言うか。要するに行動に注意深さが足りないのだ。
大人になっても変わらない、変えられずにいる自分の欠点を、ハマナスの実をかじり思った。
「注意深くあれ。一瞬一瞬立ち止まり、よくよく注意をしてから行動せよ」
自分の傍らに立ち、常に言い聞かせる、もう一人の自分が必要だ。
まあ、熊に引っ掻かれない程度には成長し、注意もできるようになってはいると思うんだけど。油断かな。

茎は棘だらけなので、注意が必要です。オレンジ色が可愛い。

真っ赤に熟れたものを、3つだけ収穫しました。

半分に切ってみると、こんなに種がありました。
味も、すっぱいだけで美味しいとは言えません。
ジャムやお茶にする理由が、よく判りました。

バラ科のハマナスの実は、ローズヒップとも呼ばれ、栄養価が高いらしい。
生でも食べられるというのでさっそく洗ってかじってみる。
「わ、種だらけ」
酸味と一緒に広がったのは、種の食感。失敗した。新しいものを半分に切ってみると、実の中身は種の部分が大半をしめている。その種部分をとってから、皮についた実の部分を食べるべきだったのだ。生で食べられると調べて安心し、油断したのであった。
こういう失敗が、子どもの頃からよくある。
両親の田舎である北海道で、木彫りの人形などを売る店に繋がれていた子熊に引っ掻かれたのも、わたしだけだった。
「可愛い!」と、つい手を出し、がりっとやられたのだ。今考えるに恐ろしいが、熊は絵本などに登場する可愛らしいものという認識だったのだろう。同じようにして、ペットショップで子猿にも引っ掻かれているから、学習しないと言うか何と言うか。要するに行動に注意深さが足りないのだ。
大人になっても変わらない、変えられずにいる自分の欠点を、ハマナスの実をかじり思った。
「注意深くあれ。一瞬一瞬立ち止まり、よくよく注意をしてから行動せよ」
自分の傍らに立ち、常に言い聞かせる、もう一人の自分が必要だ。
まあ、熊に引っ掻かれない程度には成長し、注意もできるようになってはいると思うんだけど。油断かな。
茎は棘だらけなので、注意が必要です。オレンジ色が可愛い。
真っ赤に熟れたものを、3つだけ収穫しました。
半分に切ってみると、こんなに種がありました。
味も、すっぱいだけで美味しいとは言えません。
ジャムやお茶にする理由が、よく判りました。
『炎上する君』
「絶望するな。俺達には西加奈子がいる。」
帯にかかれた、又吉直樹の言葉である。
又吉オススメの西加奈子の短編集『炎上する君』(角川文庫)を、読んだ。
不思議テイストいっぱいの短編ばかり8編、集めた本だ。
表題作は、足が炎上している男がいるという噂を聞いた二人の女性の物語。
梨田、三十二歳は、親友、浜中と共に、男に媚びることなく生きてきた。
以下本文から。
小学校のときから、いやさ、物心ついたときから、私は、自分が女であることを呪っていた。女であるがために、容姿の品定めをされ、性欲の対象としてあらねばならない。そして、不細工であると宣告された者は、生きる価値さえないような待遇を受ける。私は、女、それも不細工な女であるということで、いわれのない迫害を受けてきた。小さな頃から、ずっと。ずっと。女であることを、捨てたかった。だからといって、男にはなりたくなかった。女の品定めをし、無恥な性欲をもてあます、阿呆な男には。
女にも男にもなりたくない私は、では、何だったのだろうか。
西加奈子ってすごいなあと思うとき、大抵それは、人間の根底を深く深く見つめようと、これでもかというほど掘り下げていくところにある。足が炎上するという現実ではありえない設定の小説であっても、主人公達は真剣に自分を見つめ、生きている。そして女にも男にもなりたくなかった私は、ついに恋に落ちるのだ。以下本文から。
恋愛のさなかにいる君、恋の詩をつづる君、恋の歌を歌う君よ。
周囲の人間に、馬鹿にされるだろう、笑われるだろう、身の程知らずだと、おのれを恥じる気持ちにも、なるだろう。だがそれが、何だというのか。君は戦闘にいる。恋という戦闘のさなかにいる。誰がそれを笑うことが出来ようか。
君は炎上している。その炎は、きっと誰かを照らす。煌々と。熱く。
恋 = 炎上、という比喩、などと簡単に言うなかれ。ああ、こういう気持ちだよ! と、すとんと腑に落ちるほど、リアルに胸に迫ってきたのだ。

表紙の絵も、西加奈子が描いたものです。多才な人なんですね。
解説は又吉直樹。帯の文句も、その解説文から抜き出しています。

帯にかかれた、又吉直樹の言葉である。
又吉オススメの西加奈子の短編集『炎上する君』(角川文庫)を、読んだ。
不思議テイストいっぱいの短編ばかり8編、集めた本だ。
表題作は、足が炎上している男がいるという噂を聞いた二人の女性の物語。
梨田、三十二歳は、親友、浜中と共に、男に媚びることなく生きてきた。
以下本文から。
小学校のときから、いやさ、物心ついたときから、私は、自分が女であることを呪っていた。女であるがために、容姿の品定めをされ、性欲の対象としてあらねばならない。そして、不細工であると宣告された者は、生きる価値さえないような待遇を受ける。私は、女、それも不細工な女であるということで、いわれのない迫害を受けてきた。小さな頃から、ずっと。ずっと。女であることを、捨てたかった。だからといって、男にはなりたくなかった。女の品定めをし、無恥な性欲をもてあます、阿呆な男には。
女にも男にもなりたくない私は、では、何だったのだろうか。
西加奈子ってすごいなあと思うとき、大抵それは、人間の根底を深く深く見つめようと、これでもかというほど掘り下げていくところにある。足が炎上するという現実ではありえない設定の小説であっても、主人公達は真剣に自分を見つめ、生きている。そして女にも男にもなりたくなかった私は、ついに恋に落ちるのだ。以下本文から。
恋愛のさなかにいる君、恋の詩をつづる君、恋の歌を歌う君よ。
周囲の人間に、馬鹿にされるだろう、笑われるだろう、身の程知らずだと、おのれを恥じる気持ちにも、なるだろう。だがそれが、何だというのか。君は戦闘にいる。恋という戦闘のさなかにいる。誰がそれを笑うことが出来ようか。
君は炎上している。その炎は、きっと誰かを照らす。煌々と。熱く。
恋 = 炎上、という比喩、などと簡単に言うなかれ。ああ、こういう気持ちだよ! と、すとんと腑に落ちるほど、リアルに胸に迫ってきたのだ。
表紙の絵も、西加奈子が描いたものです。多才な人なんですね。
解説は又吉直樹。帯の文句も、その解説文から抜き出しています。
ネムの葉は、おじぎしない
ネムノキに花が咲いている。綿毛のようにふわふわした濃いピンク色の花だ。
車で走っていると市内のあちらこちらで見かける。高い木の上に咲くネムの花を愛でつつ走るのも、この季節ならではの楽しみだ。
庭にネムノキを植えてはいないが、ネムの葉と似たような植物が伸びてきた。まだ何者であるか不明だが、抜かずに置いてある。しかし、ネムノキは種から芽を出し十年経たないと花が咲かないという。判明する前に枯れるか抜かれるかしてしまうかも知れない。
その葉っぱ。子どもの頃、学校に植えてあったオジギソウとよく似ている。あまり似ているので、つい触って確かめてしまった。オジギソウは、触るとすぐに葉を閉じるのがおもしろく、人気の植物だったのだ。
だが、葉は閉じなかった。オジギソウではないということだけは判明した。そのオジギソウ、調べるとネムノキ科の植物だった。どうりで似ているはずだ。
不思議なもので、ネムノキの葉を見るまで、オジギソウのことなどこれっぽっちも思い出さなかったというのに、不意に記憶は甦るものである。
小学校の砂埃舞う校庭や、校舎の前の植え込みや、ひんやりした廊下、瓶に入った牛乳なども同時に浮かんでは、消えていった。

花はふわふわしていて、鳥の羽根のようです。
長く伸びた先がピンク色の糸状の部分は、雄しべだそうです。

高い場所で上を向いて咲いています。もう咲き終えたものもありました。

オジギソウ似(?)の葉っぱも綺麗です。細長い葉が規則正しく並んで。
夜になると、この葉が閉じることから、ネムノキと名づけられたとか。
やっぱり、オジギソウの仲間なんですね。

車で走っていると市内のあちらこちらで見かける。高い木の上に咲くネムの花を愛でつつ走るのも、この季節ならではの楽しみだ。
庭にネムノキを植えてはいないが、ネムの葉と似たような植物が伸びてきた。まだ何者であるか不明だが、抜かずに置いてある。しかし、ネムノキは種から芽を出し十年経たないと花が咲かないという。判明する前に枯れるか抜かれるかしてしまうかも知れない。
その葉っぱ。子どもの頃、学校に植えてあったオジギソウとよく似ている。あまり似ているので、つい触って確かめてしまった。オジギソウは、触るとすぐに葉を閉じるのがおもしろく、人気の植物だったのだ。
だが、葉は閉じなかった。オジギソウではないということだけは判明した。そのオジギソウ、調べるとネムノキ科の植物だった。どうりで似ているはずだ。
不思議なもので、ネムノキの葉を見るまで、オジギソウのことなどこれっぽっちも思い出さなかったというのに、不意に記憶は甦るものである。
小学校の砂埃舞う校庭や、校舎の前の植え込みや、ひんやりした廊下、瓶に入った牛乳なども同時に浮かんでは、消えていった。
花はふわふわしていて、鳥の羽根のようです。
長く伸びた先がピンク色の糸状の部分は、雄しべだそうです。
高い場所で上を向いて咲いています。もう咲き終えたものもありました。
オジギソウ似(?)の葉っぱも綺麗です。細長い葉が規則正しく並んで。
夜になると、この葉が閉じることから、ネムノキと名づけられたとか。
やっぱり、オジギソウの仲間なんですね。
雨の日はよく眠れる
夏バテしたなと思ってから寝苦しい夜が続いていたが、雨が降り、ようやくぐっすり眠れた。気温が下がったせいでは、たぶんない。エアコンのない我が家だが、ここ山梨県は北杜市では真夏でも夜には25℃以下になる。気温とは関係なく、雨だからよく眠れたのだ。
子ども達が幼かった頃を思い出すと、やはり雨の日には、ことんと眠りにつき、物音に目覚めることもなくよく眠った。外で身体を動かしたりせずとも、不思議とよく眠るのが雨の日だったのだ。
雨の日によく眠れる理由としては、湿度が睡眠に適しているからとか、雨音が子守唄代わりになるからとか、様々あげられているらしいが、満月、満潮に生まれる赤ん坊が多いのと同じように、何か宇宙規模の大きな力が働いているようにも感じる。
だとすると、そんな理由から起こる宇宙規模の衝動も、人にはあるのかも知れない。満月の夜は吠えたくなるとか、雨が降ると訳もなく掃除がしたくなるとか。わたし的には、よく眠れることをありがたく受け入れているだけだが、雨の日に無性にやりたくなる何か、ありますか?

雨に湿った隣りの林です。木々の緑は雨がうれしそうですね。

庭のムクゲも咲き始めました。雨を仰ぐように上を向いて咲いています。

子ども達が幼かった頃を思い出すと、やはり雨の日には、ことんと眠りにつき、物音に目覚めることもなくよく眠った。外で身体を動かしたりせずとも、不思議とよく眠るのが雨の日だったのだ。
雨の日によく眠れる理由としては、湿度が睡眠に適しているからとか、雨音が子守唄代わりになるからとか、様々あげられているらしいが、満月、満潮に生まれる赤ん坊が多いのと同じように、何か宇宙規模の大きな力が働いているようにも感じる。
だとすると、そんな理由から起こる宇宙規模の衝動も、人にはあるのかも知れない。満月の夜は吠えたくなるとか、雨が降ると訳もなく掃除がしたくなるとか。わたし的には、よく眠れることをありがたく受け入れているだけだが、雨の日に無性にやりたくなる何か、ありますか?
雨に湿った隣りの林です。木々の緑は雨がうれしそうですね。
庭のムクゲも咲き始めました。雨を仰ぐように上を向いて咲いています。
『ちょうちんそで』
江國香織『ちょうちんそで』(新潮文庫)を読んだ。
過去に傷を抱える五十代の女性、雛子の物語だ。雛子は、高齢者向きマンションにひとりで暮らし「架空の妹」と日々会話する。以下本文から。
「六番街の入口のところに、おもちゃ屋さんがあったでしょう? 一部分だけタバコ屋さんの」
雛子は言った。
「私たち、よくあそこにタバコを買いに行かされたわね」
姉妹の父親は物書きで、ヘヴィ・スモーカーだった。家で仕事をしていたので、タバコが切れると娘のどちらかを呼んで「お役目、果たすか?」と訊いた。そして、娘がタバコを買って帰ると「お役目、ご苦労」と言った。
「行かされた」
架空の妹はこたえる。
「委任状を持って」と。
「委任状! そうだったわね。たしかに持たされた」
思いだし、可笑しくなって、雛子は笑う。几帳面だった父は、子供にタバコは売れない、と店の人が言ったときのために、と、その都度委任状を作成した。
雛子の妹は、実際には行方不明だ。雛子の居場所はすぐに判るはずなのに、妹は連絡をしてこない。だから雛子は、妹を探すことをとうに止めていた。
家族を捨て、かけおちし、その男も失った雛子は今、元夫に養われる形で高齢者向けマンションで暮らしている。子ども達も自分を恨んでいるのだろうと思うと会うのも怖い。想像を絶するほどの孤独。という言葉を思い浮かべたが、解説の綿矢りさはかいている。
「雛子はいつも一人だけど辛い記憶につながるはずの過去を、大切に慈しみ愛してきたおかげで、どんなときも孤独ではない」
愛する妹は、自らの意思で離れていった。捨てられた、ということもできる。そのことに傷つきながらも、妹と過ごした記憶がまた雛子を救っているのだ。
傷ついた記憶を忘れ去ることだけが、その過去を乗り越える道、という訳ではないのかも知れない。
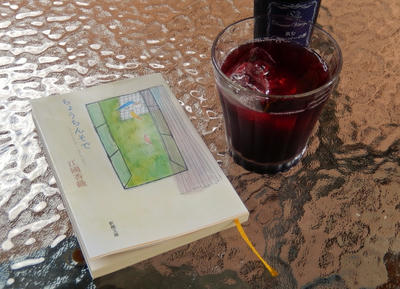
物語は、様々な人々の視点から描かれていました。
雛子、その息子ふたり、息子の恋人、同じマンションに住む2組の夫婦、
遠く離れた外国に住む小学生の女の子、の目線で魅力的に語られていきます。
(ブルーベリーのお酢を飲みながら、読みました)

過去に傷を抱える五十代の女性、雛子の物語だ。雛子は、高齢者向きマンションにひとりで暮らし「架空の妹」と日々会話する。以下本文から。
「六番街の入口のところに、おもちゃ屋さんがあったでしょう? 一部分だけタバコ屋さんの」
雛子は言った。
「私たち、よくあそこにタバコを買いに行かされたわね」
姉妹の父親は物書きで、ヘヴィ・スモーカーだった。家で仕事をしていたので、タバコが切れると娘のどちらかを呼んで「お役目、果たすか?」と訊いた。そして、娘がタバコを買って帰ると「お役目、ご苦労」と言った。
「行かされた」
架空の妹はこたえる。
「委任状を持って」と。
「委任状! そうだったわね。たしかに持たされた」
思いだし、可笑しくなって、雛子は笑う。几帳面だった父は、子供にタバコは売れない、と店の人が言ったときのために、と、その都度委任状を作成した。
雛子の妹は、実際には行方不明だ。雛子の居場所はすぐに判るはずなのに、妹は連絡をしてこない。だから雛子は、妹を探すことをとうに止めていた。
家族を捨て、かけおちし、その男も失った雛子は今、元夫に養われる形で高齢者向けマンションで暮らしている。子ども達も自分を恨んでいるのだろうと思うと会うのも怖い。想像を絶するほどの孤独。という言葉を思い浮かべたが、解説の綿矢りさはかいている。
「雛子はいつも一人だけど辛い記憶につながるはずの過去を、大切に慈しみ愛してきたおかげで、どんなときも孤独ではない」
愛する妹は、自らの意思で離れていった。捨てられた、ということもできる。そのことに傷つきながらも、妹と過ごした記憶がまた雛子を救っているのだ。
傷ついた記憶を忘れ去ることだけが、その過去を乗り越える道、という訳ではないのかも知れない。
物語は、様々な人々の視点から描かれていました。
雛子、その息子ふたり、息子の恋人、同じマンションに住む2組の夫婦、
遠く離れた外国に住む小学生の女の子、の目線で魅力的に語られていきます。
(ブルーベリーのお酢を飲みながら、読みました)
夜明け前に聴いた波音
目覚めると、波の音がした。
夢だ、と思った。ここ山梨県には海はない。
まだ夜明け前。外は真っ暗だ。
波は大きく小さく、その音を響かせている。ザーッと打ち寄せては、サーッとひいていく。それを繰り返している。
海か、と思う。家の向こうに海が広がっているのもいいかも知れないと、夢うつつで考える。
そのとき、枕元の蝋燭ライトが消えた。サーモスタットで夜明けの頃に消えるようになっている。その様子があまりにリアルで一気に現実に引き戻された。
それは夢でも何でもなく、聴こえていたのはヒグラシの鳴き声だった。
カナカナカナと鳴くというが、文字にするとまるで違う。寄せる波音に近い、まとまった高音のカナカナカナなのだった。

東側の林の木にとまっていた、アブラゼミです。
ヒグラシは、昼間、何処にいるのかな。
日が暮れるころだけじゃなく、夜明け前にも、集団で鳴くんですね。

夢だ、と思った。ここ山梨県には海はない。
まだ夜明け前。外は真っ暗だ。
波は大きく小さく、その音を響かせている。ザーッと打ち寄せては、サーッとひいていく。それを繰り返している。
海か、と思う。家の向こうに海が広がっているのもいいかも知れないと、夢うつつで考える。
そのとき、枕元の蝋燭ライトが消えた。サーモスタットで夜明けの頃に消えるようになっている。その様子があまりにリアルで一気に現実に引き戻された。
それは夢でも何でもなく、聴こえていたのはヒグラシの鳴き声だった。
カナカナカナと鳴くというが、文字にするとまるで違う。寄せる波音に近い、まとまった高音のカナカナカナなのだった。
東側の林の木にとまっていた、アブラゼミです。
ヒグラシは、昼間、何処にいるのかな。
日が暮れるころだけじゃなく、夜明け前にも、集団で鳴くんですね。
『ホテルカクタス』
江國香織の『ホテルカクタス』(集英社文庫)を再読していて、最近似たようなことがあったというシーンに出くわした。
古びたアパート『ホテルカクタス』に住むきゅうりと数字の2と帽子、三人の友情の物語。そのなかの『ある日曜日の発見』という話で、きゅうりと数字の2は、雑貨屋でばったり会い、たがいに驚く。普段親しくしている友人の姿が、外で見るとまるで違って見えたのだ。
きゅうりには、数字の2がこんなふうに見えた。
「日曜だっていうのにワイシャツとズボンなんか着ちゃって、新聞なんか買って、おまけにその新聞の買い方がきどっていて、つまりこう片手でさ、小銭を渡すと同時に新聞を受けとっただろう? まるでどっかの嫌味な役場づとめ野郎みたいに見えたから、あやうくきみだとわからないところだったよ」
そして、数字の2には、きゅうりがこんなぐあいに。
「いかにも筋肉自慢って感じで、これみよがしのランニングシャツがね、なんていうか、ちんぴらっぽかった。アパートから雑貨屋までは歩いて五分もかからないのに、わざわざサングラスを頭にのっけてるしさ、どっかの、しゃれのめした不良かと思っちゃたよ」
最近、末娘ともそうだが、夫とも外で待ち合わせることが多い。先日も都内の駅で待ち合わせていて、向こうから歩いてくる夫が見えた。すぐに判ったのだが、あれ? こんな雰囲気だったっけ。と首をかしげていると、夫も言った。「不思議な格好してるね。誰かと思ったよ」特別新しい服を着ていた訳でもなく、わたしとしてはごく普通の格好だったのだけれど。
行き交う人いきれのなか、すべての人がきっと別の顔を持っているのだと思った。外見からだけでは見ることのできない本来の姿を。しかしまた街中を闊歩する夫の姿も、本来の姿なのかも知れないとも思うのだった。
さて。物語の続き。きゅうりと数字の2は、帽子を呼び出す。外で見る帽子がどんな感じなのかを知りたかったのだ。

螺旋階段が美しい表紙です。なかにもカラーの絵がたくさん入っています。

古びたアパート『ホテルカクタス』に住むきゅうりと数字の2と帽子、三人の友情の物語。そのなかの『ある日曜日の発見』という話で、きゅうりと数字の2は、雑貨屋でばったり会い、たがいに驚く。普段親しくしている友人の姿が、外で見るとまるで違って見えたのだ。
きゅうりには、数字の2がこんなふうに見えた。
「日曜だっていうのにワイシャツとズボンなんか着ちゃって、新聞なんか買って、おまけにその新聞の買い方がきどっていて、つまりこう片手でさ、小銭を渡すと同時に新聞を受けとっただろう? まるでどっかの嫌味な役場づとめ野郎みたいに見えたから、あやうくきみだとわからないところだったよ」
そして、数字の2には、きゅうりがこんなぐあいに。
「いかにも筋肉自慢って感じで、これみよがしのランニングシャツがね、なんていうか、ちんぴらっぽかった。アパートから雑貨屋までは歩いて五分もかからないのに、わざわざサングラスを頭にのっけてるしさ、どっかの、しゃれのめした不良かと思っちゃたよ」
最近、末娘ともそうだが、夫とも外で待ち合わせることが多い。先日も都内の駅で待ち合わせていて、向こうから歩いてくる夫が見えた。すぐに判ったのだが、あれ? こんな雰囲気だったっけ。と首をかしげていると、夫も言った。「不思議な格好してるね。誰かと思ったよ」特別新しい服を着ていた訳でもなく、わたしとしてはごく普通の格好だったのだけれど。
行き交う人いきれのなか、すべての人がきっと別の顔を持っているのだと思った。外見からだけでは見ることのできない本来の姿を。しかしまた街中を闊歩する夫の姿も、本来の姿なのかも知れないとも思うのだった。
さて。物語の続き。きゅうりと数字の2は、帽子を呼び出す。外で見る帽子がどんな感じなのかを知りたかったのだ。
螺旋階段が美しい表紙です。なかにもカラーの絵がたくさん入っています。
苔生す森で
早くも夏バテをした。
身体じゅうが思うように動かず一日じゅうごろごろしていると、夫がドライブに行こうと誘う。車に乗っているだけならなんとかなりそうなので、気分転換に出かけることにした。彼が連れて行ってくれたのは、尾白川渓谷。森のなかを少し歩けば川に出る場所で、以前も涼みに来た記憶がある。
森はこのところの雨で、たっぷり湿っていた。全体的に苔生しているのだが、その苔が水を吸い、歩くと靴が沈むほどだ。森じゅうがひんやりと冷たい。深呼吸すると、湿り気が冷たさが、わたしのなかにも入ってきた。それは、思いのほか心地よかった。もしかしたら身体じゅうが乾いていたのかも知れない。
何度も、深呼吸をしながら歩き、声には出さず夫に感謝した。

杉の木の根もとにも、苔がびっしり。芽を出しているのはクヌギかな。

竹宇駒ヶ岳神社の入口です。灯篭も苔生していました。

ベンチはその用途を放棄し、苔玉ならぬ苔ベンチに進化中。

ベンチの上には、杉の新芽が出たり枯れたりしています。

近くには吊り橋がありました。台風の跡を思わせる濁流が流れていました。

身体じゅうが思うように動かず一日じゅうごろごろしていると、夫がドライブに行こうと誘う。車に乗っているだけならなんとかなりそうなので、気分転換に出かけることにした。彼が連れて行ってくれたのは、尾白川渓谷。森のなかを少し歩けば川に出る場所で、以前も涼みに来た記憶がある。
森はこのところの雨で、たっぷり湿っていた。全体的に苔生しているのだが、その苔が水を吸い、歩くと靴が沈むほどだ。森じゅうがひんやりと冷たい。深呼吸すると、湿り気が冷たさが、わたしのなかにも入ってきた。それは、思いのほか心地よかった。もしかしたら身体じゅうが乾いていたのかも知れない。
何度も、深呼吸をしながら歩き、声には出さず夫に感謝した。
杉の木の根もとにも、苔がびっしり。芽を出しているのはクヌギかな。
竹宇駒ヶ岳神社の入口です。灯篭も苔生していました。
ベンチはその用途を放棄し、苔玉ならぬ苔ベンチに進化中。
ベンチの上には、杉の新芽が出たり枯れたりしています。
近くには吊り橋がありました。台風の跡を思わせる濁流が流れていました。
胸のなかの波紋と蓮の花
買い物に行く途中の道で、夫が突然思い立ったように言った。
「そういえば、蓮、もう咲いてるよね?」
「そうだね。もう咲いてるね。でもどうかな。午後だし」
蓮の花が綺麗に開くのは、午前中なのだそうだ。しかし、台風は通り過ぎたが台風一過の快晴とはいかず空は曇っている。蓮がまた、昼前だと勘違いしても可笑しくないような天気だ。
少しだけ回り道をして蓮池に寄ってみると、やはり咲いていた。咲き終えた花の跡も多く、満開の季節は過ぎたのだと判ったが、綺麗に咲いている花も見ることができた。このあいだ寄った時には、まだこれからだと思っていたのに、季節は気づかぬうちに早送りしていたのだ。日々何をしていたのだろうと思うが、たいしたことはしていない。普通に暮らすことがあわただしいのだと言えば、それはそうかも知れない。
凛と咲く蓮の花を見て、胸のなかにある小さな池を思った。たいしたこともしていない日々なのだが、それでも毎日様々な事象がそこに波紋を広げていく。いくつもの波紋が重なり胸がざわついて眠れない夜もある。蓮の花は、そんなわたしの小さな池に広がる波紋を、静かに見つめているようだった。生きていれば、誰の胸のなかからも波紋がなくなることはないのだろう。それでも蓮の花を見ていると、胸がしんとしてくるように感じるのは何故だろう。

開ききった蓮の花は、微笑んでいるかのようです。

こちらは、二輪仲良く一緒に風に揺られていました。

これを見ると、ああ、レンコンなんだなあと思います。

蕾もまた味わいがあります。かたい蕾もまだ少しありました。

「そういえば、蓮、もう咲いてるよね?」
「そうだね。もう咲いてるね。でもどうかな。午後だし」
蓮の花が綺麗に開くのは、午前中なのだそうだ。しかし、台風は通り過ぎたが台風一過の快晴とはいかず空は曇っている。蓮がまた、昼前だと勘違いしても可笑しくないような天気だ。
少しだけ回り道をして蓮池に寄ってみると、やはり咲いていた。咲き終えた花の跡も多く、満開の季節は過ぎたのだと判ったが、綺麗に咲いている花も見ることができた。このあいだ寄った時には、まだこれからだと思っていたのに、季節は気づかぬうちに早送りしていたのだ。日々何をしていたのだろうと思うが、たいしたことはしていない。普通に暮らすことがあわただしいのだと言えば、それはそうかも知れない。
凛と咲く蓮の花を見て、胸のなかにある小さな池を思った。たいしたこともしていない日々なのだが、それでも毎日様々な事象がそこに波紋を広げていく。いくつもの波紋が重なり胸がざわついて眠れない夜もある。蓮の花は、そんなわたしの小さな池に広がる波紋を、静かに見つめているようだった。生きていれば、誰の胸のなかからも波紋がなくなることはないのだろう。それでも蓮の花を見ていると、胸がしんとしてくるように感じるのは何故だろう。
開ききった蓮の花は、微笑んでいるかのようです。
こちらは、二輪仲良く一緒に風に揺られていました。
これを見ると、ああ、レンコンなんだなあと思います。
蕾もまた味わいがあります。かたい蕾もまだ少しありました。
HN:
水月さえ
性別:
女性
自己紹介:
本を読むのが好き。昼寝が好き。ドライブが好き。陶器屋や雑貨屋巡りが好き。アジアン雑貨ならなお好き。ビールはカールスバーグの生がいちばん好き。そして、スペインを旅して以来、スペイン大好き。何をするにも、のんびりゆっくりが、好き。
ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com
(☆を@に変えてください)
ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com
(☆を@に変えてください)
