はりねずみが眠るとき
昼寝をしながら本を読み、ビールを空けて料理する日々
『天使はモップを持って』
引き続き、近藤史恵を読んでいる。『天使はモップを持って』(文春文庫)
オフィスを舞台にしたミステリー要素たっぷりの連作短編集だ。
変わっているのは、探偵役をするビルの掃除を仕事にする人物が、モップなど似合わないようなファッショナブルな格好をした十代の女の子だということだ。彼女はキリコ。主人公はそのビルの会社に入社したばかりの大介だ。
そんなキリコと大介が、社内で起こった謎を解いていく。キリコが掃除する場所には、意識せずとも謎解きのヒントが隠されている。ゴミを捨てる人も、汚す人も、そこを掃除する人間がどう思うかなど考えることはない。翌朝、オフィスが綺麗になっていてもそれは当然のことであり、掃除をする人が入ったのだと想像力を働かせる人は少ない。キリコが掃除する場所には常に人の心の隙や油断が落ちていて、そこから人の本性が見え隠れもする場所なのである。
謎が解けたことで、そんな人の心根を垣間見てしまい、人間関係の修復に悩む大介に、キリコは言う。以下本文から。
「大丈夫、世の中はお掃除と一緒だよ。汚れたらきれいにすればいい。また、汚れちゃうかもしれないけど、また、きれいにすればいい」
「でも、絶対、落ちない汚れだってあるだろう」
「そりゃあ、ね。でも大部分は、根気とテクニックさえあれば、なんとかなっちゃうもんよ。コツとしては早いほど落ちやすいってこともあるけどね」
掃除の仕事に誇りを持って、毎日を過ごしているキリコは、本当に眩しい。

カラフルな表紙のキリコ、とっても可愛いです。
続編『モップの精は深夜に現れる』も、おもしろかった!

オフィスを舞台にしたミステリー要素たっぷりの連作短編集だ。
変わっているのは、探偵役をするビルの掃除を仕事にする人物が、モップなど似合わないようなファッショナブルな格好をした十代の女の子だということだ。彼女はキリコ。主人公はそのビルの会社に入社したばかりの大介だ。
そんなキリコと大介が、社内で起こった謎を解いていく。キリコが掃除する場所には、意識せずとも謎解きのヒントが隠されている。ゴミを捨てる人も、汚す人も、そこを掃除する人間がどう思うかなど考えることはない。翌朝、オフィスが綺麗になっていてもそれは当然のことであり、掃除をする人が入ったのだと想像力を働かせる人は少ない。キリコが掃除する場所には常に人の心の隙や油断が落ちていて、そこから人の本性が見え隠れもする場所なのである。
謎が解けたことで、そんな人の心根を垣間見てしまい、人間関係の修復に悩む大介に、キリコは言う。以下本文から。
「大丈夫、世の中はお掃除と一緒だよ。汚れたらきれいにすればいい。また、汚れちゃうかもしれないけど、また、きれいにすればいい」
「でも、絶対、落ちない汚れだってあるだろう」
「そりゃあ、ね。でも大部分は、根気とテクニックさえあれば、なんとかなっちゃうもんよ。コツとしては早いほど落ちやすいってこともあるけどね」
掃除の仕事に誇りを持って、毎日を過ごしているキリコは、本当に眩しい。
カラフルな表紙のキリコ、とっても可愛いです。
続編『モップの精は深夜に現れる』も、おもしろかった!
『ダークルーム』
近藤史恵の短編集『ダークルーム』(角川文庫)を、読んだ。
8編のミステリーは、裏表紙で、こう紹介されている。
「立ちはだかる現実に絶望し、窮地に立たされた人間たちが取った異常な行動とは。日常に潜む狂気と、明かされる驚愕の真相」
高級フレンチレストランで、毎晩ひとり食事する美女。自殺した元恋人が、新しい恋人に乗り移ったと疑う男。双子の美少女モデル達と、殺されたマネージャー。何も知らないふりをしつつ、兄の恋人に激しい嫉妬を抱く妹。
ひとつひとつのストーリーが、静かな寒気を呼ぶ恐ろしさを持っていた。
なかでも、いちばん好きだったのはラストに収められた書き下ろし『北緯六十度の恋』だ。多佳子は恋人の園子とフィンランドを訪れた。3年前から同性愛者の園子の恋人として振舞ってきた多佳子には、園子への復讐の計画があった。以下本文から。
草というのを聞いたことがあるだろうか。
わたしは子供の頃、弟の部屋でこっそり読んだ忍者漫画で知った。
草の任務についた忍者は、その標的の土地に普通の人として移り住む。そして三年、五年、ときによっては何十年も忍者としての自分を隠して、そこで生活を営むのだ。そして、すっかりそこに溶け込んだ頃に、任務遂行の知らせがやってくる。それが暗殺や、重要な情報を雇い主に流すことだったとしても、すっかりその土地やコミュニティに溶け込んでしまった草は疑われない。簡単に敵の懐に忍び込み、任務を遂行することができるのだ。
多佳子は、共に3年の月日を過ごし、手酷い裏切りで園子の傷が深くなることを確信し、計画を実行しようとしていた。だが、その先に待っていたものは。
もし何年も信頼し合ってきたと思える人が「草」と同じことをしようとしていたら? そう考えると空恐ろしくなるが、また逆に、人は、人を信頼することで生きているのだと、本を閉じ、強く思ったのだった。

カフェラテを飲みながら、読書タイム。夏に合う涼しくなる小説です。

8編のミステリーは、裏表紙で、こう紹介されている。
「立ちはだかる現実に絶望し、窮地に立たされた人間たちが取った異常な行動とは。日常に潜む狂気と、明かされる驚愕の真相」
高級フレンチレストランで、毎晩ひとり食事する美女。自殺した元恋人が、新しい恋人に乗り移ったと疑う男。双子の美少女モデル達と、殺されたマネージャー。何も知らないふりをしつつ、兄の恋人に激しい嫉妬を抱く妹。
ひとつひとつのストーリーが、静かな寒気を呼ぶ恐ろしさを持っていた。
なかでも、いちばん好きだったのはラストに収められた書き下ろし『北緯六十度の恋』だ。多佳子は恋人の園子とフィンランドを訪れた。3年前から同性愛者の園子の恋人として振舞ってきた多佳子には、園子への復讐の計画があった。以下本文から。
草というのを聞いたことがあるだろうか。
わたしは子供の頃、弟の部屋でこっそり読んだ忍者漫画で知った。
草の任務についた忍者は、その標的の土地に普通の人として移り住む。そして三年、五年、ときによっては何十年も忍者としての自分を隠して、そこで生活を営むのだ。そして、すっかりそこに溶け込んだ頃に、任務遂行の知らせがやってくる。それが暗殺や、重要な情報を雇い主に流すことだったとしても、すっかりその土地やコミュニティに溶け込んでしまった草は疑われない。簡単に敵の懐に忍び込み、任務を遂行することができるのだ。
多佳子は、共に3年の月日を過ごし、手酷い裏切りで園子の傷が深くなることを確信し、計画を実行しようとしていた。だが、その先に待っていたものは。
もし何年も信頼し合ってきたと思える人が「草」と同じことをしようとしていたら? そう考えると空恐ろしくなるが、また逆に、人は、人を信頼することで生きているのだと、本を閉じ、強く思ったのだった。
カフェラテを飲みながら、読書タイム。夏に合う涼しくなる小説です。
『六番目の小夜子』
ずっと読みたいと思いつつ開くことのなかった恩田陸デビュー作『六番目の小夜子』(新潮文庫)を、読んだ。いやー、おもしろかった。
事前情報は何も見ずに読み始め、タイトルと表紙から学園モノのホラーかと思い込んでいたせいか、何処で人が死ぬ? 何処で怖いシーンが? と緊張してもいたのだが、ホラーではなかった。100%ホラーじゃないと言い切る自信はないのだが。
舞台は地方の高校。進学校であるその高校には、奇妙な言い伝えが受け継がれていた。卒業していく「サヨコ」に鍵を渡された生徒が次の「サヨコ」になる、というものだ。「サヨコ」は三年ごとに行動を起こさなくてはならない。ストーリーは、行動を起こすべき「サヨコ」が、六番目の年の物語だ。そこへ、沙世子という名の美しく謎めいた転校生がやってきた。
読み終えて感じたのは、学校という場所の不思議さだった。以下本文から。
溢れる学生服とセーラー服に、雅子は圧倒されそうになる。
黒と紺の塊が、くっつき、離れ、思い思いのエネルギーを放射している。それでいて、塊全体が一つの意思を持ち、うごめいているかのようだ。学校というのは、なんて変なところなのだろう。同じ歳の男の子と女の子がこんなにたくさん集まって、あの狭く四角い部屋にずらりと机を並べているなんて。なんと特異で、なんと優遇された、そしてなんと閉じられた空間なのだろう。
学校という入れ物のなかには、そこを通り過ぎていく生徒達だからこそ生まれる一体感があり、小説はその閉鎖された場所での一体感が起こす不思議を描いていた。この小説を読み、学校の怪談などが生まれるのも、やはりその「閉鎖された場所での一体感」から来るのではないかと、腑に落ちた。
読後、様々なレビューを読むと、張りめぐらされた伏線が回収されていない、最後までよく判らないとの意見が多く見られた。だが、わたしは学校という場所が起こす不思議を垣間見ることができ、満ち足りた気分で本を閉じたのだ。

赤に、無表情なセーラー服の女生徒が印象的な表紙です。

事前情報は何も見ずに読み始め、タイトルと表紙から学園モノのホラーかと思い込んでいたせいか、何処で人が死ぬ? 何処で怖いシーンが? と緊張してもいたのだが、ホラーではなかった。100%ホラーじゃないと言い切る自信はないのだが。
舞台は地方の高校。進学校であるその高校には、奇妙な言い伝えが受け継がれていた。卒業していく「サヨコ」に鍵を渡された生徒が次の「サヨコ」になる、というものだ。「サヨコ」は三年ごとに行動を起こさなくてはならない。ストーリーは、行動を起こすべき「サヨコ」が、六番目の年の物語だ。そこへ、沙世子という名の美しく謎めいた転校生がやってきた。
読み終えて感じたのは、学校という場所の不思議さだった。以下本文から。
溢れる学生服とセーラー服に、雅子は圧倒されそうになる。
黒と紺の塊が、くっつき、離れ、思い思いのエネルギーを放射している。それでいて、塊全体が一つの意思を持ち、うごめいているかのようだ。学校というのは、なんて変なところなのだろう。同じ歳の男の子と女の子がこんなにたくさん集まって、あの狭く四角い部屋にずらりと机を並べているなんて。なんと特異で、なんと優遇された、そしてなんと閉じられた空間なのだろう。
学校という入れ物のなかには、そこを通り過ぎていく生徒達だからこそ生まれる一体感があり、小説はその閉鎖された場所での一体感が起こす不思議を描いていた。この小説を読み、学校の怪談などが生まれるのも、やはりその「閉鎖された場所での一体感」から来るのではないかと、腑に落ちた。
読後、様々なレビューを読むと、張りめぐらされた伏線が回収されていない、最後までよく判らないとの意見が多く見られた。だが、わたしは学校という場所が起こす不思議を垣間見ることができ、満ち足りた気分で本を閉じたのだ。
赤に、無表情なセーラー服の女生徒が印象的な表紙です。
『炎上する君』
「絶望するな。俺達には西加奈子がいる。」
帯にかかれた、又吉直樹の言葉である。
又吉オススメの西加奈子の短編集『炎上する君』(角川文庫)を、読んだ。
不思議テイストいっぱいの短編ばかり8編、集めた本だ。
表題作は、足が炎上している男がいるという噂を聞いた二人の女性の物語。
梨田、三十二歳は、親友、浜中と共に、男に媚びることなく生きてきた。
以下本文から。
小学校のときから、いやさ、物心ついたときから、私は、自分が女であることを呪っていた。女であるがために、容姿の品定めをされ、性欲の対象としてあらねばならない。そして、不細工であると宣告された者は、生きる価値さえないような待遇を受ける。私は、女、それも不細工な女であるということで、いわれのない迫害を受けてきた。小さな頃から、ずっと。ずっと。女であることを、捨てたかった。だからといって、男にはなりたくなかった。女の品定めをし、無恥な性欲をもてあます、阿呆な男には。
女にも男にもなりたくない私は、では、何だったのだろうか。
西加奈子ってすごいなあと思うとき、大抵それは、人間の根底を深く深く見つめようと、これでもかというほど掘り下げていくところにある。足が炎上するという現実ではありえない設定の小説であっても、主人公達は真剣に自分を見つめ、生きている。そして女にも男にもなりたくなかった私は、ついに恋に落ちるのだ。以下本文から。
恋愛のさなかにいる君、恋の詩をつづる君、恋の歌を歌う君よ。
周囲の人間に、馬鹿にされるだろう、笑われるだろう、身の程知らずだと、おのれを恥じる気持ちにも、なるだろう。だがそれが、何だというのか。君は戦闘にいる。恋という戦闘のさなかにいる。誰がそれを笑うことが出来ようか。
君は炎上している。その炎は、きっと誰かを照らす。煌々と。熱く。
恋 = 炎上、という比喩、などと簡単に言うなかれ。ああ、こういう気持ちだよ! と、すとんと腑に落ちるほど、リアルに胸に迫ってきたのだ。

表紙の絵も、西加奈子が描いたものです。多才な人なんですね。
解説は又吉直樹。帯の文句も、その解説文から抜き出しています。

帯にかかれた、又吉直樹の言葉である。
又吉オススメの西加奈子の短編集『炎上する君』(角川文庫)を、読んだ。
不思議テイストいっぱいの短編ばかり8編、集めた本だ。
表題作は、足が炎上している男がいるという噂を聞いた二人の女性の物語。
梨田、三十二歳は、親友、浜中と共に、男に媚びることなく生きてきた。
以下本文から。
小学校のときから、いやさ、物心ついたときから、私は、自分が女であることを呪っていた。女であるがために、容姿の品定めをされ、性欲の対象としてあらねばならない。そして、不細工であると宣告された者は、生きる価値さえないような待遇を受ける。私は、女、それも不細工な女であるということで、いわれのない迫害を受けてきた。小さな頃から、ずっと。ずっと。女であることを、捨てたかった。だからといって、男にはなりたくなかった。女の品定めをし、無恥な性欲をもてあます、阿呆な男には。
女にも男にもなりたくない私は、では、何だったのだろうか。
西加奈子ってすごいなあと思うとき、大抵それは、人間の根底を深く深く見つめようと、これでもかというほど掘り下げていくところにある。足が炎上するという現実ではありえない設定の小説であっても、主人公達は真剣に自分を見つめ、生きている。そして女にも男にもなりたくなかった私は、ついに恋に落ちるのだ。以下本文から。
恋愛のさなかにいる君、恋の詩をつづる君、恋の歌を歌う君よ。
周囲の人間に、馬鹿にされるだろう、笑われるだろう、身の程知らずだと、おのれを恥じる気持ちにも、なるだろう。だがそれが、何だというのか。君は戦闘にいる。恋という戦闘のさなかにいる。誰がそれを笑うことが出来ようか。
君は炎上している。その炎は、きっと誰かを照らす。煌々と。熱く。
恋 = 炎上、という比喩、などと簡単に言うなかれ。ああ、こういう気持ちだよ! と、すとんと腑に落ちるほど、リアルに胸に迫ってきたのだ。
表紙の絵も、西加奈子が描いたものです。多才な人なんですね。
解説は又吉直樹。帯の文句も、その解説文から抜き出しています。
『ちょうちんそで』
江國香織『ちょうちんそで』(新潮文庫)を読んだ。
過去に傷を抱える五十代の女性、雛子の物語だ。雛子は、高齢者向きマンションにひとりで暮らし「架空の妹」と日々会話する。以下本文から。
「六番街の入口のところに、おもちゃ屋さんがあったでしょう? 一部分だけタバコ屋さんの」
雛子は言った。
「私たち、よくあそこにタバコを買いに行かされたわね」
姉妹の父親は物書きで、ヘヴィ・スモーカーだった。家で仕事をしていたので、タバコが切れると娘のどちらかを呼んで「お役目、果たすか?」と訊いた。そして、娘がタバコを買って帰ると「お役目、ご苦労」と言った。
「行かされた」
架空の妹はこたえる。
「委任状を持って」と。
「委任状! そうだったわね。たしかに持たされた」
思いだし、可笑しくなって、雛子は笑う。几帳面だった父は、子供にタバコは売れない、と店の人が言ったときのために、と、その都度委任状を作成した。
雛子の妹は、実際には行方不明だ。雛子の居場所はすぐに判るはずなのに、妹は連絡をしてこない。だから雛子は、妹を探すことをとうに止めていた。
家族を捨て、かけおちし、その男も失った雛子は今、元夫に養われる形で高齢者向けマンションで暮らしている。子ども達も自分を恨んでいるのだろうと思うと会うのも怖い。想像を絶するほどの孤独。という言葉を思い浮かべたが、解説の綿矢りさはかいている。
「雛子はいつも一人だけど辛い記憶につながるはずの過去を、大切に慈しみ愛してきたおかげで、どんなときも孤独ではない」
愛する妹は、自らの意思で離れていった。捨てられた、ということもできる。そのことに傷つきながらも、妹と過ごした記憶がまた雛子を救っているのだ。
傷ついた記憶を忘れ去ることだけが、その過去を乗り越える道、という訳ではないのかも知れない。
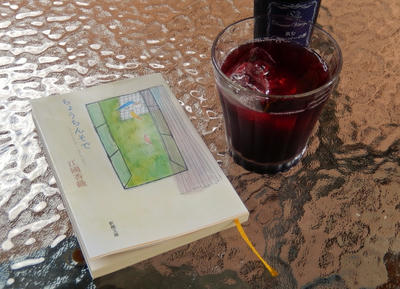
物語は、様々な人々の視点から描かれていました。
雛子、その息子ふたり、息子の恋人、同じマンションに住む2組の夫婦、
遠く離れた外国に住む小学生の女の子、の目線で魅力的に語られていきます。
(ブルーベリーのお酢を飲みながら、読みました)

過去に傷を抱える五十代の女性、雛子の物語だ。雛子は、高齢者向きマンションにひとりで暮らし「架空の妹」と日々会話する。以下本文から。
「六番街の入口のところに、おもちゃ屋さんがあったでしょう? 一部分だけタバコ屋さんの」
雛子は言った。
「私たち、よくあそこにタバコを買いに行かされたわね」
姉妹の父親は物書きで、ヘヴィ・スモーカーだった。家で仕事をしていたので、タバコが切れると娘のどちらかを呼んで「お役目、果たすか?」と訊いた。そして、娘がタバコを買って帰ると「お役目、ご苦労」と言った。
「行かされた」
架空の妹はこたえる。
「委任状を持って」と。
「委任状! そうだったわね。たしかに持たされた」
思いだし、可笑しくなって、雛子は笑う。几帳面だった父は、子供にタバコは売れない、と店の人が言ったときのために、と、その都度委任状を作成した。
雛子の妹は、実際には行方不明だ。雛子の居場所はすぐに判るはずなのに、妹は連絡をしてこない。だから雛子は、妹を探すことをとうに止めていた。
家族を捨て、かけおちし、その男も失った雛子は今、元夫に養われる形で高齢者向けマンションで暮らしている。子ども達も自分を恨んでいるのだろうと思うと会うのも怖い。想像を絶するほどの孤独。という言葉を思い浮かべたが、解説の綿矢りさはかいている。
「雛子はいつも一人だけど辛い記憶につながるはずの過去を、大切に慈しみ愛してきたおかげで、どんなときも孤独ではない」
愛する妹は、自らの意思で離れていった。捨てられた、ということもできる。そのことに傷つきながらも、妹と過ごした記憶がまた雛子を救っているのだ。
傷ついた記憶を忘れ去ることだけが、その過去を乗り越える道、という訳ではないのかも知れない。
物語は、様々な人々の視点から描かれていました。
雛子、その息子ふたり、息子の恋人、同じマンションに住む2組の夫婦、
遠く離れた外国に住む小学生の女の子、の目線で魅力的に語られていきます。
(ブルーベリーのお酢を飲みながら、読みました)
『ホテルカクタス』
江國香織の『ホテルカクタス』(集英社文庫)を再読していて、最近似たようなことがあったというシーンに出くわした。
古びたアパート『ホテルカクタス』に住むきゅうりと数字の2と帽子、三人の友情の物語。そのなかの『ある日曜日の発見』という話で、きゅうりと数字の2は、雑貨屋でばったり会い、たがいに驚く。普段親しくしている友人の姿が、外で見るとまるで違って見えたのだ。
きゅうりには、数字の2がこんなふうに見えた。
「日曜だっていうのにワイシャツとズボンなんか着ちゃって、新聞なんか買って、おまけにその新聞の買い方がきどっていて、つまりこう片手でさ、小銭を渡すと同時に新聞を受けとっただろう? まるでどっかの嫌味な役場づとめ野郎みたいに見えたから、あやうくきみだとわからないところだったよ」
そして、数字の2には、きゅうりがこんなぐあいに。
「いかにも筋肉自慢って感じで、これみよがしのランニングシャツがね、なんていうか、ちんぴらっぽかった。アパートから雑貨屋までは歩いて五分もかからないのに、わざわざサングラスを頭にのっけてるしさ、どっかの、しゃれのめした不良かと思っちゃたよ」
最近、末娘ともそうだが、夫とも外で待ち合わせることが多い。先日も都内の駅で待ち合わせていて、向こうから歩いてくる夫が見えた。すぐに判ったのだが、あれ? こんな雰囲気だったっけ。と首をかしげていると、夫も言った。「不思議な格好してるね。誰かと思ったよ」特別新しい服を着ていた訳でもなく、わたしとしてはごく普通の格好だったのだけれど。
行き交う人いきれのなか、すべての人がきっと別の顔を持っているのだと思った。外見からだけでは見ることのできない本来の姿を。しかしまた街中を闊歩する夫の姿も、本来の姿なのかも知れないとも思うのだった。
さて。物語の続き。きゅうりと数字の2は、帽子を呼び出す。外で見る帽子がどんな感じなのかを知りたかったのだ。

螺旋階段が美しい表紙です。なかにもカラーの絵がたくさん入っています。

古びたアパート『ホテルカクタス』に住むきゅうりと数字の2と帽子、三人の友情の物語。そのなかの『ある日曜日の発見』という話で、きゅうりと数字の2は、雑貨屋でばったり会い、たがいに驚く。普段親しくしている友人の姿が、外で見るとまるで違って見えたのだ。
きゅうりには、数字の2がこんなふうに見えた。
「日曜だっていうのにワイシャツとズボンなんか着ちゃって、新聞なんか買って、おまけにその新聞の買い方がきどっていて、つまりこう片手でさ、小銭を渡すと同時に新聞を受けとっただろう? まるでどっかの嫌味な役場づとめ野郎みたいに見えたから、あやうくきみだとわからないところだったよ」
そして、数字の2には、きゅうりがこんなぐあいに。
「いかにも筋肉自慢って感じで、これみよがしのランニングシャツがね、なんていうか、ちんぴらっぽかった。アパートから雑貨屋までは歩いて五分もかからないのに、わざわざサングラスを頭にのっけてるしさ、どっかの、しゃれのめした不良かと思っちゃたよ」
最近、末娘ともそうだが、夫とも外で待ち合わせることが多い。先日も都内の駅で待ち合わせていて、向こうから歩いてくる夫が見えた。すぐに判ったのだが、あれ? こんな雰囲気だったっけ。と首をかしげていると、夫も言った。「不思議な格好してるね。誰かと思ったよ」特別新しい服を着ていた訳でもなく、わたしとしてはごく普通の格好だったのだけれど。
行き交う人いきれのなか、すべての人がきっと別の顔を持っているのだと思った。外見からだけでは見ることのできない本来の姿を。しかしまた街中を闊歩する夫の姿も、本来の姿なのかも知れないとも思うのだった。
さて。物語の続き。きゅうりと数字の2は、帽子を呼び出す。外で見る帽子がどんな感じなのかを知りたかったのだ。
螺旋階段が美しい表紙です。なかにもカラーの絵がたくさん入っています。
『そこへ行くな』
井上荒野の短編集『そこへ行くな』(集英社文庫)を読んだ。
やはり短編の『もう二度と食べたくない甘いもの』(祥伝社文庫)に不思議な魅力を感じたから手に取ったのだが、こちらの方が数段ヘビーで、何度も中断してしまった。それが悪いというのではない。胸のなかに悪いものが広がるのを感じながらも小説のなかへなかへと落ちていくように入りこんでしまった。
タイトルの表題作にあたるものはない。すべての短編が『そこへ行くな』をテーマとしているのだ。「そこ」はひとつひとつ違う。結婚だったり、死だったり、金だったり、セックスだったり、ネットだったり、いじめだったり。
越えてはいけない一線を越えてしまう人の愚かさや悲しさが、垣間見える。
一話目の『遊園地』は、12年も同棲していて、ふたりの子どもも小学生になったのに、夫だと思っていた籍を入れていない男に、じつは妻子がいるのだと判ってしまう。以下本文から。
気がつくと、数字に取り囲まれている。いつも数字のことばかり考えている。たとえば、純一郎さんの今度の出張は七日間(もしかしたら十日間)。今回、彼が家で過ごしたのは三日間。その前の出張は二十六日間 ― 二十日と言っていたが、六日延びた。
あるいは、子供たちの年齢のこと。太郎は七歳。あの町で見た、あの女性の子供は三歳。あの子供が生まれたときに太郎は四歳で、わたしは三十八歳だった。三年前。あの女性はまだ十代だったのではないか。
数字のことばかり考えるのは、たしかなものはそれだけだからだ。
こんなふうに、主人公達の心理描写が深く深く描かれていて、起こった出来事以上にヘビーだと感じたのだと思う。
そして読み終えて何より考えたのは、負の吸引力についてだ。してはいけないと思えば思うほど、それに引きつけられ、過ちを犯してしまう様は『鶴女房』で「絶対に覗かないでください」と言われ、障子の向こうを覗かずにはいられなかった男の心理とも似ている。入ってはいけない危険な場所だからこそふらふらと吸い寄せられる時が、誰しもきっとあるのだと呆然としたのだった。

ドアの向こう側には何があるのだろう、と思わせるような表紙です。
全体の白が希望を表すようにも感じますが、タイトルが効いています。
2011年に第6回中央公論文芸賞を受賞した短編集です。


やはり短編の『もう二度と食べたくない甘いもの』(祥伝社文庫)に不思議な魅力を感じたから手に取ったのだが、こちらの方が数段ヘビーで、何度も中断してしまった。それが悪いというのではない。胸のなかに悪いものが広がるのを感じながらも小説のなかへなかへと落ちていくように入りこんでしまった。
タイトルの表題作にあたるものはない。すべての短編が『そこへ行くな』をテーマとしているのだ。「そこ」はひとつひとつ違う。結婚だったり、死だったり、金だったり、セックスだったり、ネットだったり、いじめだったり。
越えてはいけない一線を越えてしまう人の愚かさや悲しさが、垣間見える。
一話目の『遊園地』は、12年も同棲していて、ふたりの子どもも小学生になったのに、夫だと思っていた籍を入れていない男に、じつは妻子がいるのだと判ってしまう。以下本文から。
気がつくと、数字に取り囲まれている。いつも数字のことばかり考えている。たとえば、純一郎さんの今度の出張は七日間(もしかしたら十日間)。今回、彼が家で過ごしたのは三日間。その前の出張は二十六日間 ― 二十日と言っていたが、六日延びた。
あるいは、子供たちの年齢のこと。太郎は七歳。あの町で見た、あの女性の子供は三歳。あの子供が生まれたときに太郎は四歳で、わたしは三十八歳だった。三年前。あの女性はまだ十代だったのではないか。
数字のことばかり考えるのは、たしかなものはそれだけだからだ。
こんなふうに、主人公達の心理描写が深く深く描かれていて、起こった出来事以上にヘビーだと感じたのだと思う。
そして読み終えて何より考えたのは、負の吸引力についてだ。してはいけないと思えば思うほど、それに引きつけられ、過ちを犯してしまう様は『鶴女房』で「絶対に覗かないでください」と言われ、障子の向こうを覗かずにはいられなかった男の心理とも似ている。入ってはいけない危険な場所だからこそふらふらと吸い寄せられる時が、誰しもきっとあるのだと呆然としたのだった。
ドアの向こう側には何があるのだろう、と思わせるような表紙です。
全体の白が希望を表すようにも感じますが、タイトルが効いています。
2011年に第6回中央公論文芸賞を受賞した短編集です。
みんな、いつも旅してる
一昨日、夕焼けが綺麗だった。
落ちていく太陽を見ると、普段は忘れていることだが、ああ、地球は回っているんだなと思う。そして夕焼けを見ながら、不意に川上弘美の短編集『猫を拾いに』(マガジンハウス)に収められた『旅は、無料』という小説の一節を思い出した。以下本文から。
砂浜に座って、わたしと圭司は、しばらくお喋りをした。風が冷たかったので、頬がまっかになった。
「旅行、またいっぱいしたいね」
わたしが言うと、圭司はうなずいた。
「いっぱい仕事して、旅行のお金、ためるよ、わたし」
「そんなに、ためなくて、いいよ」
「でも」
「こないだ本読んでたらさ」
圭司はそこで、ばさりとあおむけになった。
「こんなことが書いてあった。地球上の生活にはお金がかかるかもしれないけど、太陽の周りを年に一周する旅が無料でついてくる、って」
目の前が、突然ぱあっと明るくなった。日を隠していた雲が、移動したのだ。
「そうかあ、いつも旅してるのか、わたしたち」
「そうだよ」
みんな、いつも旅してるのさ。夕焼けがそう言っているように思えたのだ。

我が家の東側からは、八ヶ岳が少しだけ見えています。

南側に建てられたソーラーパネルにも、夕焼けが映っていました。

落ちていく太陽を見ると、普段は忘れていることだが、ああ、地球は回っているんだなと思う。そして夕焼けを見ながら、不意に川上弘美の短編集『猫を拾いに』(マガジンハウス)に収められた『旅は、無料』という小説の一節を思い出した。以下本文から。
砂浜に座って、わたしと圭司は、しばらくお喋りをした。風が冷たかったので、頬がまっかになった。
「旅行、またいっぱいしたいね」
わたしが言うと、圭司はうなずいた。
「いっぱい仕事して、旅行のお金、ためるよ、わたし」
「そんなに、ためなくて、いいよ」
「でも」
「こないだ本読んでたらさ」
圭司はそこで、ばさりとあおむけになった。
「こんなことが書いてあった。地球上の生活にはお金がかかるかもしれないけど、太陽の周りを年に一周する旅が無料でついてくる、って」
目の前が、突然ぱあっと明るくなった。日を隠していた雲が、移動したのだ。
「そうかあ、いつも旅してるのか、わたしたち」
「そうだよ」
みんな、いつも旅してるのさ。夕焼けがそう言っているように思えたのだ。
我が家の東側からは、八ヶ岳が少しだけ見えています。
南側に建てられたソーラーパネルにも、夕焼けが映っていました。
『恋の棺』
田辺聖子の『恋の棺(ひつぎ)』を読んだ。
『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)に収められた短編だ。
29歳の宇禰(うね)は、姉の息子、つまり甥である19歳の有二に惹かれていた。そんな彼女の独り言のような小説だ。三人称でかかれているがぶれることなく宇禰の目線で進んでいくので、独り言のように感じたのかも知れない。
全体を通して、宇禰の有二を見つめる眼差しがとても優しく、半分子どもを可愛がっているようでもあり、ときにふっと微笑んでしまうようなラブストーリーだった。ラストは西條八十の詩の引用「語りえぬ二人の恋なれば われらが棺の上に草生ふる日にも 絶えて知るひとの無かるべし」で終わるのだが、読後もやわらかな微笑ましさが胸から消えることはなかった。
重要なキーワードは「二重人格」だ。宇禰は、別れる前に夫から投げつけられたその言葉に傷つき、自分の多面性を客観視しては乾いた傷を眺めるように生きていた。有二との恋は、その傷を昇華させていく。以下本文から。
宇禰のやさしい微笑からは、恋の棺を埋めた人とは見えないだろうと宇禰自身、思われる。しかし宇禰はこの悦楽を尖鋭化するために、二度と有二と機会を持とうとは思わないのだ。宇禰はそういう決意を匕首(あいくち)のようにかくし持ちながら、微笑んでいる自分の「二重人格」が、いまはいとしく思えている。これこそ、女の生きる喜びだった。
解説の山田詠美が、かいている。
「田辺小説の主人公達はみな、人生をいつくしむ才能に恵まれている」と。
それを読み、胸に残る微笑ましさの源がなんだったのかが、腑に落ちた。
人生をいつくしむ才能。百回となえたら、わたしにもそなわるだろうか。

最近、昔読んだ山本文緒の短編を、読み漁っています。
それが日常化していたなかで読んだ、田辺聖子の短編は新鮮でした。


『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)に収められた短編だ。
29歳の宇禰(うね)は、姉の息子、つまり甥である19歳の有二に惹かれていた。そんな彼女の独り言のような小説だ。三人称でかかれているがぶれることなく宇禰の目線で進んでいくので、独り言のように感じたのかも知れない。
全体を通して、宇禰の有二を見つめる眼差しがとても優しく、半分子どもを可愛がっているようでもあり、ときにふっと微笑んでしまうようなラブストーリーだった。ラストは西條八十の詩の引用「語りえぬ二人の恋なれば われらが棺の上に草生ふる日にも 絶えて知るひとの無かるべし」で終わるのだが、読後もやわらかな微笑ましさが胸から消えることはなかった。
重要なキーワードは「二重人格」だ。宇禰は、別れる前に夫から投げつけられたその言葉に傷つき、自分の多面性を客観視しては乾いた傷を眺めるように生きていた。有二との恋は、その傷を昇華させていく。以下本文から。
宇禰のやさしい微笑からは、恋の棺を埋めた人とは見えないだろうと宇禰自身、思われる。しかし宇禰はこの悦楽を尖鋭化するために、二度と有二と機会を持とうとは思わないのだ。宇禰はそういう決意を匕首(あいくち)のようにかくし持ちながら、微笑んでいる自分の「二重人格」が、いまはいとしく思えている。これこそ、女の生きる喜びだった。
解説の山田詠美が、かいている。
「田辺小説の主人公達はみな、人生をいつくしむ才能に恵まれている」と。
それを読み、胸に残る微笑ましさの源がなんだったのかが、腑に落ちた。
人生をいつくしむ才能。百回となえたら、わたしにもそなわるだろうか。
最近、昔読んだ山本文緒の短編を、読み漁っています。
それが日常化していたなかで読んだ、田辺聖子の短編は新鮮でした。
『待つ』
太宰治の『待つ』を読んだ。『女生徒』(角川文庫)収録の短編だ。
読んだばかりの『太宰治の辞書』に出てきた小説で、『待つ』は本当に短く、掌編とも言えるだろう。戦時中、駅で若い女が誰かを待っている。ただそれだけの話、と言ってもいいような小説だ。以下本文から。
私の待っているのは、あなたではない。それでは一体、私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っています。胸を躍らせて待っているのだ。
彼女は、いったい何を待っているのだろう。それはラストまで判らない。
だけど、いや。だから共感した。わたしだって、たぶん何かを待っている。無粋な言い方かもしれないが、生きているってそういうことなんじゃないかな。

角川文庫のこの装幀には違和感がありました。でも十代の子達には、
こういうのが手にとりやすいのかな? 個人的には、違う気がしますが。

読んだばかりの『太宰治の辞書』に出てきた小説で、『待つ』は本当に短く、掌編とも言えるだろう。戦時中、駅で若い女が誰かを待っている。ただそれだけの話、と言ってもいいような小説だ。以下本文から。
私の待っているのは、あなたではない。それでは一体、私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っています。胸を躍らせて待っているのだ。
彼女は、いったい何を待っているのだろう。それはラストまで判らない。
だけど、いや。だから共感した。わたしだって、たぶん何かを待っている。無粋な言い方かもしれないが、生きているってそういうことなんじゃないかな。
角川文庫のこの装幀には違和感がありました。でも十代の子達には、
こういうのが手にとりやすいのかな? 個人的には、違う気がしますが。
『太宰治の辞書』
北村薫の最新刊『太宰治の辞書』(新潮社)を読んだ。
「〈円紫さんと私〉シリーズの続きが出た」
埼玉の大学に通う末娘からメールがあったのは先月のこと。驚き喜んで、本屋に買いに走った。第5弾である前作『朝霧』が出版されてから17年経っている。続きが出るなどとは青天の霹靂だった。
「買ったよ。読んだら貸してあげる」とメールを返す。
彼女からはひと言「やった!」と返ってきた。貧乏学生である彼女には、新刊を買う余裕はないようだし、根強い人気のあるシリーズだけに図書館でも待ち数が多く、手に取れるのはずいぶん先のことだと思っていたのだろう。
シリーズ初め、主人公で語り手である〈私〉は大学生だった。落語家の円紫師匠とともに日常に潜む謎を解いていくアマチュア探偵によるコージーミステリーだ。だがその〈私〉と円紫さんの根っこにあった読書マニアとも言えるほどの本を愛する姿勢が物語を動かし、やがて本の世界の謎までも解こうという方向へと進んでいく。
『太宰治の辞書』は、前作から二十年が経ち、本好き高じて出版社で働くようになった〈私〉が、太宰の小説『女生徒』に出会い、そのなかに登場する辞書が、どの辞書だったのかを探していく話だ。そして〈私〉は、やがて辞書とは別のものにたどりついていくのだった。
読んでいて、ときにふっと笑ってしまった。センスの良いユーモアに笑わせられるところはもちろんあったが、そういうところで、ではない。
「この人、本当に本が好きなんだなぁ」と〈私〉と作者を重ね、その、もう恥も外聞もなく好きで好きでしょうがないのだと身体じゅうで言っているような文章が、微笑ましく思えてしまったのだ。
そんなことを思いつつぺらぺらとページを捲っていて、すごいものを見つけた。本の巻頭の献辞である。「愛する妻に捧ぐ ―」みたいな感じで「本に ―」とある。思わず吹き出してしまった。爆笑だ。
そう言えば、うちにもそんな本好きがもう一人いたなぁと、シリーズ1作目『空飛ぶ馬』を読んでいた息子の背中を思い出した。
十年ほど前の冬、雪が心配される大学センター入試の前日のことだった。受験のために本断ちしていた彼は、その朝居間のテーブルに『空飛ぶ馬』を見つけ、何かに憑かれるかのように読み始めてしまった。置いておいたわたしの失敗だと後悔したが、読み始めたものを途中でやめて試験に臨むよりもいいだろうと、放っておいた。自分でも今本を読んでいるときではないと判っていた彼は「座れば?」というわたしの言葉にも答えず、結局そこに立ったまま、1時間と少しかけてその文庫本を読み終えてしまったのだ。
その文庫は今、埼玉の末娘の部屋にある。息子より7つ下の彼女が、クリスマスに〈円紫さんと私〉シリーズが欲しい。家にあるのでいいから、と言ったのは中学生のときだった。
『太宰治の辞書』が末娘から返却されたら、息子に送ってやろうかと、あのときの背中を思い浮かべ考えた。それとも彼はもう、読んだだろうか。

デビュー作でもある『空飛ぶ馬』から始まり『夜の蝉』『秋の花』
『六の宮の姫君』『朝霧』と続きます。再読したくなりました。
『太宰治の辞書』に出てきた青森土産の「生まれて墨ませんべい」が
実在するか調べるてみたら、ほんとにあった(笑) → こちら

「〈円紫さんと私〉シリーズの続きが出た」
埼玉の大学に通う末娘からメールがあったのは先月のこと。驚き喜んで、本屋に買いに走った。第5弾である前作『朝霧』が出版されてから17年経っている。続きが出るなどとは青天の霹靂だった。
「買ったよ。読んだら貸してあげる」とメールを返す。
彼女からはひと言「やった!」と返ってきた。貧乏学生である彼女には、新刊を買う余裕はないようだし、根強い人気のあるシリーズだけに図書館でも待ち数が多く、手に取れるのはずいぶん先のことだと思っていたのだろう。
シリーズ初め、主人公で語り手である〈私〉は大学生だった。落語家の円紫師匠とともに日常に潜む謎を解いていくアマチュア探偵によるコージーミステリーだ。だがその〈私〉と円紫さんの根っこにあった読書マニアとも言えるほどの本を愛する姿勢が物語を動かし、やがて本の世界の謎までも解こうという方向へと進んでいく。
『太宰治の辞書』は、前作から二十年が経ち、本好き高じて出版社で働くようになった〈私〉が、太宰の小説『女生徒』に出会い、そのなかに登場する辞書が、どの辞書だったのかを探していく話だ。そして〈私〉は、やがて辞書とは別のものにたどりついていくのだった。
読んでいて、ときにふっと笑ってしまった。センスの良いユーモアに笑わせられるところはもちろんあったが、そういうところで、ではない。
「この人、本当に本が好きなんだなぁ」と〈私〉と作者を重ね、その、もう恥も外聞もなく好きで好きでしょうがないのだと身体じゅうで言っているような文章が、微笑ましく思えてしまったのだ。
そんなことを思いつつぺらぺらとページを捲っていて、すごいものを見つけた。本の巻頭の献辞である。「愛する妻に捧ぐ ―」みたいな感じで「本に ―」とある。思わず吹き出してしまった。爆笑だ。
そう言えば、うちにもそんな本好きがもう一人いたなぁと、シリーズ1作目『空飛ぶ馬』を読んでいた息子の背中を思い出した。
十年ほど前の冬、雪が心配される大学センター入試の前日のことだった。受験のために本断ちしていた彼は、その朝居間のテーブルに『空飛ぶ馬』を見つけ、何かに憑かれるかのように読み始めてしまった。置いておいたわたしの失敗だと後悔したが、読み始めたものを途中でやめて試験に臨むよりもいいだろうと、放っておいた。自分でも今本を読んでいるときではないと判っていた彼は「座れば?」というわたしの言葉にも答えず、結局そこに立ったまま、1時間と少しかけてその文庫本を読み終えてしまったのだ。
その文庫は今、埼玉の末娘の部屋にある。息子より7つ下の彼女が、クリスマスに〈円紫さんと私〉シリーズが欲しい。家にあるのでいいから、と言ったのは中学生のときだった。
『太宰治の辞書』が末娘から返却されたら、息子に送ってやろうかと、あのときの背中を思い浮かべ考えた。それとも彼はもう、読んだだろうか。
デビュー作でもある『空飛ぶ馬』から始まり『夜の蝉』『秋の花』
『六の宮の姫君』『朝霧』と続きます。再読したくなりました。
『太宰治の辞書』に出てきた青森土産の「生まれて墨ませんべい」が
実在するか調べるてみたら、ほんとにあった(笑) → こちら
『ニシノユキヒコの恋と冒険』
とりあえず身近にある、確実に湿った恋愛が読める小説を開いた。
『ニシノユキヒコの恋と冒険』(新潮文庫)川上弘美の連作短編集。何度も読んでいて、内容は親しみ知っている。それでも開くたびに発見がある小説だ。
以下、恋する気持ちを的確に突きつけてくれる3編目の『おやすみ』から。
ばかげた恋。しびれるような、動くこともできない、うずくまった手負いのけもののような、恋。ユキヒコは、恋というものによって手負いにされたわたしを、飛び道具も使わずに、爪も牙も使わずに、いともかんたんに手に入れた。そのときわたしはどんなにかふるえたことだろう。身のうちからわきでる、ふるえ。ユキヒコにとらえられたよろこびによって溢れでたふるえ。
多少乱暴な考え方かもしれないが、だから恋をしたとか、あれがきっかけで好きになったとか、じつはすべてこじつけで、恋に落ちるのに理由なんかないんじゃないのかなと思っている。理由だなんだと考えた時点で、それはもう恋じゃないんじゃないのかなとも思っている。
衝動。理由のない心の動き。説明のつかないもの。そういうものがあるから、人間って面倒くさいのだ。
ニシノユキヒコに恋をした十人の女達はみな、理由なんてものが入りこむ余地もなく恋に落ち、ああ、ままならぬものを抱えてしまったと、後から気づく。そのときにはもう、いくら戻りたいと思っても後戻りなどできない。そして彼女達は、ニシノと出会う前などに決して戻りたいとは思わなかった。
説明のつかないものを、無理矢理、説明しようとするのはやめようよ。
質のいい恋愛小説は、いつも、わたしに呼びかける。
悩み何かに抗ったりしているとき、あれこれ理由をつけようと躍起になっている自分を、途端に俯瞰させてくれるのだ。

ピカソが恋した女達。ドラ・マールとマリー・テレーズの肖像画です。
ピカソも恋多き人だったようですが、ニシノには負けるかなぁ。

『ニシノユキヒコの恋と冒険』(新潮文庫)川上弘美の連作短編集。何度も読んでいて、内容は親しみ知っている。それでも開くたびに発見がある小説だ。
以下、恋する気持ちを的確に突きつけてくれる3編目の『おやすみ』から。
ばかげた恋。しびれるような、動くこともできない、うずくまった手負いのけもののような、恋。ユキヒコは、恋というものによって手負いにされたわたしを、飛び道具も使わずに、爪も牙も使わずに、いともかんたんに手に入れた。そのときわたしはどんなにかふるえたことだろう。身のうちからわきでる、ふるえ。ユキヒコにとらえられたよろこびによって溢れでたふるえ。
多少乱暴な考え方かもしれないが、だから恋をしたとか、あれがきっかけで好きになったとか、じつはすべてこじつけで、恋に落ちるのに理由なんかないんじゃないのかなと思っている。理由だなんだと考えた時点で、それはもう恋じゃないんじゃないのかなとも思っている。
衝動。理由のない心の動き。説明のつかないもの。そういうものがあるから、人間って面倒くさいのだ。
ニシノユキヒコに恋をした十人の女達はみな、理由なんてものが入りこむ余地もなく恋に落ち、ああ、ままならぬものを抱えてしまったと、後から気づく。そのときにはもう、いくら戻りたいと思っても後戻りなどできない。そして彼女達は、ニシノと出会う前などに決して戻りたいとは思わなかった。
説明のつかないものを、無理矢理、説明しようとするのはやめようよ。
質のいい恋愛小説は、いつも、わたしに呼びかける。
悩み何かに抗ったりしているとき、あれこれ理由をつけようと躍起になっている自分を、途端に俯瞰させてくれるのだ。
ピカソが恋した女達。ドラ・マールとマリー・テレーズの肖像画です。
ピカソも恋多き人だったようですが、ニシノには負けるかなぁ。
『クローバー』
青春恋愛小説と歌われる『クローバー』(角川書店)を、再読した。7年ほど前に読んだ本だが、急に読みたくなったのだ。何がって言えば、恋愛小説が。だが本を開き最初に思ったのは、島本理生ってこんなにおもしろかったっけ?ということ だ。そこには恋愛小説の湿り気はまるで感じられず、華子と冬治(とうじ)のやりとりがからっと晴れた空のような潔さでかかれていて、それは、ぽんぽんと次々はじけていくポップコーンを連想させるほど軽快だった。
ふたりで暮らす華子と冬治は、大学2年。双子の姉弟だ。帯の紹介文を借りると、ワガママで思いこみが激しい女子力全開の華子。やや人生不完全燃焼気味の理科系男子、冬治。そのふたりが、まるで友達のように、そして友達にはあり得ない正直さで、たがいの恋愛について語り、口出しし、心配し、傍観したり見ていられなくなって世話を焼いたりする。自分と全く違うタイプのもう一人の自分を持っているようなふたりなのだ。
性格上、振り回されるのは大抵冬治の方で、わがままな華子に呆れつつも、放っておけない。それでもバランスがとれているのは、ふたりが培ってきた関係性の成せる技なのだろう。以下本文から。
「こうしない? 次の電車が入ってきたとき、私たちの正面のドアから最初に降りてきたのが女の人だったら、雪村さんを追いかける。もし男の人だったら、彼女のことは忘れる」
あまりに強引な提案に僕はあっけにとられた。だけど華子は真顔で続けた。
「私は正直、冬治がこのまま彼女と別れても身勝手だとは思わない。この先、どうなるか分からない恋人のために将来を変えろなんて、誰にも言えない。だけど迷ってるなら、もう預けちゃいなよ」
「誰に?」
私に、と華子は答えた。
「だって子供の頃、冬治がどの玩具やお菓子を買ってもらうかで迷ったときに、決めるのはいつも私の役目だったでしょう」
ふたりの関係が魅力的に思えたのは、いくら家族でもここまで立ち入れないだろうと思うが故だ。生身の人間は傷つくのが怖い。家族であっても触れられたくない部分を正直に見せあったりはしない。しかし小説のなかのふたりは最初からその関係性の上に立ち、恋愛などなどを繰り広げていく訳で、そんなところがキラキラと光って見えたのかも知れない。
「だけどこれ、恋愛小説っていうよりは、恋愛の要素入り小説って感じかも」
そう思ってあとがきを読むと、島本理生がかいていた。
「この小説は、青春小説でも恋愛小説でもなく、モラトリアムとその終わりの物語、というとらえ方をするのが、自分の中では一番しっくりきます」
という訳で、恋愛小説を読もうという初志はまだ満たされてはいないのだが。

『クローバー』というタイトルの持つ意味は、冬治が語っていました。
「父と華子、そして僕の三人はとてもよく似ている。だけどそこに母が交ざると、途端に僕ら一家は特別な華やかに包まれる。そして僕はふいに思う。僕らはまるで三枚だと見向きもされないのに、一枚増えただけでもてはやされる四葉のようだと。もっとも母の華やかさが、僕らに幸福をもたらすだけかというと、けっしてそんなことはないのだけれど」島本理生24歳の時の作品です。

ふたりで暮らす華子と冬治は、大学2年。双子の姉弟だ。帯の紹介文を借りると、ワガママで思いこみが激しい女子力全開の華子。やや人生不完全燃焼気味の理科系男子、冬治。そのふたりが、まるで友達のように、そして友達にはあり得ない正直さで、たがいの恋愛について語り、口出しし、心配し、傍観したり見ていられなくなって世話を焼いたりする。自分と全く違うタイプのもう一人の自分を持っているようなふたりなのだ。
性格上、振り回されるのは大抵冬治の方で、わがままな華子に呆れつつも、放っておけない。それでもバランスがとれているのは、ふたりが培ってきた関係性の成せる技なのだろう。以下本文から。
「こうしない? 次の電車が入ってきたとき、私たちの正面のドアから最初に降りてきたのが女の人だったら、雪村さんを追いかける。もし男の人だったら、彼女のことは忘れる」
あまりに強引な提案に僕はあっけにとられた。だけど華子は真顔で続けた。
「私は正直、冬治がこのまま彼女と別れても身勝手だとは思わない。この先、どうなるか分からない恋人のために将来を変えろなんて、誰にも言えない。だけど迷ってるなら、もう預けちゃいなよ」
「誰に?」
私に、と華子は答えた。
「だって子供の頃、冬治がどの玩具やお菓子を買ってもらうかで迷ったときに、決めるのはいつも私の役目だったでしょう」
ふたりの関係が魅力的に思えたのは、いくら家族でもここまで立ち入れないだろうと思うが故だ。生身の人間は傷つくのが怖い。家族であっても触れられたくない部分を正直に見せあったりはしない。しかし小説のなかのふたりは最初からその関係性の上に立ち、恋愛などなどを繰り広げていく訳で、そんなところがキラキラと光って見えたのかも知れない。
「だけどこれ、恋愛小説っていうよりは、恋愛の要素入り小説って感じかも」
そう思ってあとがきを読むと、島本理生がかいていた。
「この小説は、青春小説でも恋愛小説でもなく、モラトリアムとその終わりの物語、というとらえ方をするのが、自分の中では一番しっくりきます」
という訳で、恋愛小説を読もうという初志はまだ満たされてはいないのだが。
『クローバー』というタイトルの持つ意味は、冬治が語っていました。
「父と華子、そして僕の三人はとてもよく似ている。だけどそこに母が交ざると、途端に僕ら一家は特別な華やかに包まれる。そして僕はふいに思う。僕らはまるで三枚だと見向きもされないのに、一枚増えただけでもてはやされる四葉のようだと。もっとも母の華やかさが、僕らに幸福をもたらすだけかというと、けっしてそんなことはないのだけれど」島本理生24歳の時の作品です。
『窓の魚』
衝撃が走った。西加奈子の小説『窓の魚』(新潮社文庫)。
その衝撃は、冒頭から始まる。以下本文から。
バスを降りた途端、細い風が、耳の付け根を怖がるように撫でていった。あまりにもささやかで、頼りない。始まったばかりの小さな川から吹いてくるからだろうか。川は山の緑を映してゆらゆらと細く、若い女の静脈のように見える。紅葉にはまだ早かったが、この褪せた緑の方が、私は絢爛な紅葉よりも、きっと好きだ。目に乱暴に飛び込んでくるのではなく、目をつむった後にじわりと思い出すような、深い緑である。
描写だとか比喩だとかそういうこと以前に、何だこの文章は、と唖然とした。
かっこよすぎる! としか表現できないことが嫌になる。
2組の恋人達、ナツとアキオ、ハルナとトウヤマが、山深い温泉宿で一夜を過ごし、翌朝、一体の死体が発見される。小説は、その一夜を、四人それぞれの視点から描いている。
冒頭は、ナツ。次は、トウヤマの章。
空は、油断していると、すぐに色を変える。ついさっきまで見えていた木の幹や、足元に落ちた何かの葉や、煙草の吸殻などが、いつの間にか目を凝らさなければ見えないようになり、ああしまった、そう思って上を向くと、もう遅い。薄墨を一滴垂らした、雫のようなそれが藍色に広がり、だらしなく、しかしすばやく、黒に変えてしまう。さっきまでの空の色を、黒になる前のそれを思い出そうとしても、駄目だ。それはもう、昨日の中にしかなく、俺は、これから始まる朝までの長い時間のことを思って、げんなりする。そしてだらしない夜の、その中から零れ落ちたようなあの女のことを考え、何度も舌打ちをするはめになる。
ハルナの章。
煙草の煙が、空気をどんどん汚してしまっていた。夜は、もうすっかりあたしたちを包んで、そこから出すまいとしていた。出るつもりなんて、あたしにはなかった。「トウヤマ君は?」そう聞くと、トウヤマ君はあたしを膝から突き飛ばした。何を気に入らないことがあったのだろうと、泣きそうになったけど、見上げたトウヤマ君の顔を見て、はっとした。何て綺麗な顔なのだろう。夜の影に半分体を取られている、煙草を吸わないと生きていけないこの男は、なんて綺麗な顔をしているのだろうと、思った。
アキオの章。
降りるバス停を告げていたので運転手が声をかけてくれた。あやうく乗り過ごすところだった。皆は相変わらず眠っていたし、僕はそのとき窓から見える昼間の白い月に、目を奪われていたのだ。手術着を思わせる清潔な水色の空に、誰かの目玉みたいな白い月が浮かんでいる。圧倒的であった木々の緑も、空までは届かないのか。そう思うと、心地よい絶望感のようなものが僕を包んだ。
そして、宿の女将の言葉。
私は、宿の窓に映っている、自分の顔を見ました。赤く引いた私の唇は、私の顔を走る傷のようにも、池で泳いでいる、鯉たちの、濡れた体のようにも見えました。ここから決して出ることもなく、何かを請うように、体を揺らす、魚たちの、哀しい体のように見えました。
四人ともが、いや。生きていれば誰でもが持つ閉塞感を、タイトル『窓の魚』はイメージしている。読み終えると、窓に映るモノだけではなく、目に見えるモノも見えないモノも、くっきりと見えてくるような小説だった。

東京からの帰り、特急かいじの車窓で。窓に魚は映りませんでした。

その衝撃は、冒頭から始まる。以下本文から。
バスを降りた途端、細い風が、耳の付け根を怖がるように撫でていった。あまりにもささやかで、頼りない。始まったばかりの小さな川から吹いてくるからだろうか。川は山の緑を映してゆらゆらと細く、若い女の静脈のように見える。紅葉にはまだ早かったが、この褪せた緑の方が、私は絢爛な紅葉よりも、きっと好きだ。目に乱暴に飛び込んでくるのではなく、目をつむった後にじわりと思い出すような、深い緑である。
描写だとか比喩だとかそういうこと以前に、何だこの文章は、と唖然とした。
かっこよすぎる! としか表現できないことが嫌になる。
2組の恋人達、ナツとアキオ、ハルナとトウヤマが、山深い温泉宿で一夜を過ごし、翌朝、一体の死体が発見される。小説は、その一夜を、四人それぞれの視点から描いている。
冒頭は、ナツ。次は、トウヤマの章。
空は、油断していると、すぐに色を変える。ついさっきまで見えていた木の幹や、足元に落ちた何かの葉や、煙草の吸殻などが、いつの間にか目を凝らさなければ見えないようになり、ああしまった、そう思って上を向くと、もう遅い。薄墨を一滴垂らした、雫のようなそれが藍色に広がり、だらしなく、しかしすばやく、黒に変えてしまう。さっきまでの空の色を、黒になる前のそれを思い出そうとしても、駄目だ。それはもう、昨日の中にしかなく、俺は、これから始まる朝までの長い時間のことを思って、げんなりする。そしてだらしない夜の、その中から零れ落ちたようなあの女のことを考え、何度も舌打ちをするはめになる。
ハルナの章。
煙草の煙が、空気をどんどん汚してしまっていた。夜は、もうすっかりあたしたちを包んで、そこから出すまいとしていた。出るつもりなんて、あたしにはなかった。「トウヤマ君は?」そう聞くと、トウヤマ君はあたしを膝から突き飛ばした。何を気に入らないことがあったのだろうと、泣きそうになったけど、見上げたトウヤマ君の顔を見て、はっとした。何て綺麗な顔なのだろう。夜の影に半分体を取られている、煙草を吸わないと生きていけないこの男は、なんて綺麗な顔をしているのだろうと、思った。
アキオの章。
降りるバス停を告げていたので運転手が声をかけてくれた。あやうく乗り過ごすところだった。皆は相変わらず眠っていたし、僕はそのとき窓から見える昼間の白い月に、目を奪われていたのだ。手術着を思わせる清潔な水色の空に、誰かの目玉みたいな白い月が浮かんでいる。圧倒的であった木々の緑も、空までは届かないのか。そう思うと、心地よい絶望感のようなものが僕を包んだ。
そして、宿の女将の言葉。
私は、宿の窓に映っている、自分の顔を見ました。赤く引いた私の唇は、私の顔を走る傷のようにも、池で泳いでいる、鯉たちの、濡れた体のようにも見えました。ここから決して出ることもなく、何かを請うように、体を揺らす、魚たちの、哀しい体のように見えました。
四人ともが、いや。生きていれば誰でもが持つ閉塞感を、タイトル『窓の魚』はイメージしている。読み終えると、窓に映るモノだけではなく、目に見えるモノも見えないモノも、くっきりと見えてくるような小説だった。
東京からの帰り、特急かいじの車窓で。窓に魚は映りませんでした。
『大統領の料理人』のファルシ
映画『大統領の料理人』をDVDで観た。
映像とサウンドのアクセントの一致が、とても素敵な映画だった。
フランスの片田舎で小さなレストランを営む女性シェフ、オスタンス。調理法はもちろん、素材に強くこだわりを持つ彼女は、大統領が求めた「おばあちゃんの味」を再現するため、スカウトされる。ミッテラン大統領と女性シェフの実話をもとにしたストーリーだ。
長く務めるシェフ達との確執なども描かれていたが、何より楽しめたのは、いいモノを創り上げようとするオスタンスと彼女のチームの姿勢だった。
そして、とても好きだったのは、オスタンスの助手、ニコラの台詞。
試作し続けたチーズ料理、ジョンシェを厨房で試食するシーンだ。
「ジュレが多すぎない?」と言うオスタンスに「これでいい、これだからいい」と説明する。そして、口に入れてうっとりと言う。
「これを食べると、子ども時代がよみがえる」
オスタンスの人としての魅力を理解し尊敬して成長していく彼の姿は、この映画の大切なスパイスになっていた。ジョンシェは他のシェフ達とのトラブルで、大統領の口には入らず幻の一皿となったが、試行錯誤し創り上げた昼食会の料理を食べた大統領は、ニコラと同じ言葉でオスタンスに礼を言う。
子どもの頃に何を食べたかを、身体が覚えているってことなんだろうな。それって、じつはとても大切なことなのかも。
映画のなかの料理は、もちろんものすごく美味しそうだった。だけど、日本の家庭じゃあ作れそうにないものばかり。ポルチーニやトリュフなど入手できない素材も多く、味すらも想像できない料理も多かった。そのなかで、唯一作れそうだと思ったのが「きゃべつとサーモンのファルシ」だ。
「今夜は、ワインかな」
夫がそう言って出勤していったので、ワインに合うことは間違いなさそうだしと、昨夜、挑戦してみた。まさかそれを食べ、子ども時代はよみがえらないだろうと思っていたのだけれど、子どもの頃、弟と鮭缶の背骨を取り合って喧嘩しつつ食べたことを、思い出したのだった。

「きゃべつとサーモンのファルシ」というより、
「きゃべつと鮭の重ね蒸し」になってしまいました。

全体像です。ふきんに包んで、ベジブロスで茹でました。

映像とサウンドのアクセントの一致が、とても素敵な映画だった。
フランスの片田舎で小さなレストランを営む女性シェフ、オスタンス。調理法はもちろん、素材に強くこだわりを持つ彼女は、大統領が求めた「おばあちゃんの味」を再現するため、スカウトされる。ミッテラン大統領と女性シェフの実話をもとにしたストーリーだ。
長く務めるシェフ達との確執なども描かれていたが、何より楽しめたのは、いいモノを創り上げようとするオスタンスと彼女のチームの姿勢だった。
そして、とても好きだったのは、オスタンスの助手、ニコラの台詞。
試作し続けたチーズ料理、ジョンシェを厨房で試食するシーンだ。
「ジュレが多すぎない?」と言うオスタンスに「これでいい、これだからいい」と説明する。そして、口に入れてうっとりと言う。
「これを食べると、子ども時代がよみがえる」
オスタンスの人としての魅力を理解し尊敬して成長していく彼の姿は、この映画の大切なスパイスになっていた。ジョンシェは他のシェフ達とのトラブルで、大統領の口には入らず幻の一皿となったが、試行錯誤し創り上げた昼食会の料理を食べた大統領は、ニコラと同じ言葉でオスタンスに礼を言う。
子どもの頃に何を食べたかを、身体が覚えているってことなんだろうな。それって、じつはとても大切なことなのかも。
映画のなかの料理は、もちろんものすごく美味しそうだった。だけど、日本の家庭じゃあ作れそうにないものばかり。ポルチーニやトリュフなど入手できない素材も多く、味すらも想像できない料理も多かった。そのなかで、唯一作れそうだと思ったのが「きゃべつとサーモンのファルシ」だ。
「今夜は、ワインかな」
夫がそう言って出勤していったので、ワインに合うことは間違いなさそうだしと、昨夜、挑戦してみた。まさかそれを食べ、子ども時代はよみがえらないだろうと思っていたのだけれど、子どもの頃、弟と鮭缶の背骨を取り合って喧嘩しつつ食べたことを、思い出したのだった。
「きゃべつとサーモンのファルシ」というより、
「きゃべつと鮭の重ね蒸し」になってしまいました。
全体像です。ふきんに包んで、ベジブロスで茹でました。
『ジョゼと虎と魚たち』
引き続き、田辺聖子を読んでいる。
短編集『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)だ。
もう十年以上前にことになるが『ジョゼと虎と魚たち』が映画化された際、レンタルして観た印象が強烈で、そのとき、田辺聖子をいつか読もうと思ったのだ。それから、ひと昔というほどの時間は過ぎたが、実現することができた。『朝ごはんぬき?』が新装版で復刻し、本屋に平積みされていて偶然手に取ることとなったのだが、いつか読もうと思っていたからこその偶然である。
『ジョゼ』は、文庫本で25ページ程度の短編だ。映画とは、ストーリーもだいぶ違っていたが、下肢が麻痺して車椅子に乗っているジョゼと恒夫のラブストーリーだということは、変わらない。
祖母とふたり、生活保護を受け暮らしていたジョゼは、ジョゼの言うところの「悪意の気配」によって、座っていた車椅子を押され、下り坂を転げ落ちた。それを助けたのが大学生の恒夫だった。この小説の魅力は、何と言ってもジョゼのキャラクターである。以下本文から。
「アタイなあ、これから自分の名前、ジョゼにする」
といったことがあった。
「なんでクミがジョゼになるねん」
恒夫は何が何だか分からぬ顔付きでいる。
「理由なんかない。けど、アタイはジョゼいうたほうがぴったし、やねん。
クミいう名前、放下(ほか)すわ」
「そんな簡単に名前変えられるかいな。役所『ふん』言いよらへんテ」
「役所なんかどうでもええ。アタイが自分でそうすると思てるだけでええねん。あんた、アタイのこと、ジョゼ、呼ばな返事せえへんよ。これから」
ジョゼは、他人とつるまず、障害者の集まりにも参加しない。恒夫にはいつも高飛車な態度で、車椅子に乗せてもらうのが遅れたりすると、容赦なく文句を言う。自分を捨てた父親のことを優しい人だと思って疑わず、恒夫が悪く言おうものなら、ものすごい剣幕で怒る。ジョゼは、虎が怖い。嬉しすぎると不機嫌になる。そして、魚たちを見るのが好きだ。以下本文から。
(アタイたちは死んでる。「死んだモン」になってる)
死んだモン、というのは屍体(したい)のことである。魚のような恒夫とジョゼの姿に、ジョゼは深い満足のためいきを洩らす。恒夫はいつジョゼから去るか分からないが、傍にいる限りは幸福で、それでいいとジョゼは思う。そしてジョゼは幸福を考えるとき、それは死と同義語に思える。完全無欠な幸福は、死そのものだった。
水族館で泳ぐ魚たち。屍体となった自分。そして、幸福。
どれも穏やかで、思い浮かべれば、気持ちがしんと静まっていく。

『夕ごはんたべた?』も、一緒に購入しました。分厚い文庫です。
『ジョゼと虎と魚たち』には、短編9編が収められています。
映画では、池脇千鶴がジョゼを好演していました。

短編集『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)だ。
もう十年以上前にことになるが『ジョゼと虎と魚たち』が映画化された際、レンタルして観た印象が強烈で、そのとき、田辺聖子をいつか読もうと思ったのだ。それから、ひと昔というほどの時間は過ぎたが、実現することができた。『朝ごはんぬき?』が新装版で復刻し、本屋に平積みされていて偶然手に取ることとなったのだが、いつか読もうと思っていたからこその偶然である。
『ジョゼ』は、文庫本で25ページ程度の短編だ。映画とは、ストーリーもだいぶ違っていたが、下肢が麻痺して車椅子に乗っているジョゼと恒夫のラブストーリーだということは、変わらない。
祖母とふたり、生活保護を受け暮らしていたジョゼは、ジョゼの言うところの「悪意の気配」によって、座っていた車椅子を押され、下り坂を転げ落ちた。それを助けたのが大学生の恒夫だった。この小説の魅力は、何と言ってもジョゼのキャラクターである。以下本文から。
「アタイなあ、これから自分の名前、ジョゼにする」
といったことがあった。
「なんでクミがジョゼになるねん」
恒夫は何が何だか分からぬ顔付きでいる。
「理由なんかない。けど、アタイはジョゼいうたほうがぴったし、やねん。
クミいう名前、放下(ほか)すわ」
「そんな簡単に名前変えられるかいな。役所『ふん』言いよらへんテ」
「役所なんかどうでもええ。アタイが自分でそうすると思てるだけでええねん。あんた、アタイのこと、ジョゼ、呼ばな返事せえへんよ。これから」
ジョゼは、他人とつるまず、障害者の集まりにも参加しない。恒夫にはいつも高飛車な態度で、車椅子に乗せてもらうのが遅れたりすると、容赦なく文句を言う。自分を捨てた父親のことを優しい人だと思って疑わず、恒夫が悪く言おうものなら、ものすごい剣幕で怒る。ジョゼは、虎が怖い。嬉しすぎると不機嫌になる。そして、魚たちを見るのが好きだ。以下本文から。
(アタイたちは死んでる。「死んだモン」になってる)
死んだモン、というのは屍体(したい)のことである。魚のような恒夫とジョゼの姿に、ジョゼは深い満足のためいきを洩らす。恒夫はいつジョゼから去るか分からないが、傍にいる限りは幸福で、それでいいとジョゼは思う。そしてジョゼは幸福を考えるとき、それは死と同義語に思える。完全無欠な幸福は、死そのものだった。
水族館で泳ぐ魚たち。屍体となった自分。そして、幸福。
どれも穏やかで、思い浮かべれば、気持ちがしんと静まっていく。
『夕ごはんたべた?』も、一緒に購入しました。分厚い文庫です。
『ジョゼと虎と魚たち』には、短編9編が収められています。
映画では、池脇千鶴がジョゼを好演していました。
『朝ごはんぬき?』
田辺聖子を、初めて読んだ。
『朝ごはんぬき?』(新潮文庫)1976年に出版された小説だ。
裏表紙の紹介文に「ハイ・ミス」という言葉が使われていることからも、最近かかれたものではないと判る。主人公はそのハイ・ミス。31歳で未婚の明田マリ子。ハイ・ミスという言葉も聞かなくなったが、31歳をハイ・ミスと呼ぶこと自体、今ではあり得ないんじゃないか、などと思いつつ読み始めたのだが、ページを捲る指は止まらなかった。ユーモア小説と言われるだけのことはあり、おもしろいのだ。
失恋して会社を辞めたマリ子は、女流作家秋本えりか(本名、土井ヨシ乃)の家で住み込みで働くことになった。お手伝い兼、秘書兼、イヌの散歩係だ。その家族の様子が、何ともおもしろい。
売れっ子作家のえりかは、締め切りぎりぎりにならないと原稿をかきはじめず、編集者からの電話には「いないと、言って!」と怒鳴る。えりかの夫は、そんな妻にも慣れていて、常にのんびりと傍観。放って熟睡し、マリ子に「鉄人・ねむり犀(さい)」とあだ名をつけられる。女子高生の娘、さゆりちゃんは、反抗はしないが大人とは関わりたくないと思っている様子。カップヌードル党。3人の家族は、一緒に食事をしない。マリ子は、そんな3人に何やら納得しない思いを抱きつつも、自分の仕事をきちんとこなすのだ。
以下、ねむり犀、土井氏が、帰りが遅くなったさゆりちゃんを叱るシーン。
「困った子やな。そう外食ばかりしてはあかん。子供はちゃんと、家でモノをたべる」土井氏は嘆息して「何を食べた」と好奇心にみちて聞いた。
この人、食べ物の話をするときは、とみに生き生きする。
「豚珍軒のごもく焼きそば …… 」
と、さゆりちゃんは悪事を働いたごとく、うなだれる。
「ごもく焼きそばか、あれは量が多いばかりでまずい。豚珍軒はラーメンのおつゆがうまいのです。塩味ラーメン食べればよかったのに、なんで、まずうて高うて量ばかり多いごもく焼きそばなんか、食べるのや!」
さゆりちゃんは泣きべそをかいて、もじもじする。
「もし焼きそばなら、向かいの天珍楼にすればよかったのに!」
ここまで的を外し説教できる父親って、じつにすごいと思ってしまった。
そして、蒸発(?)した土井氏を迎えた、えりか氏の台詞がまた、すごい。
「夫というものは、家に帰ればいつもいるもの、妻にさからわず、妻の邪魔をせず、要るときだけ、前へ出てくるもの、勝手にかげで自由行動することは許さん! 離婚の、蒸発の、とそういう自由も許さん …… 」
こんな家族、あり得ないと呆れつつも、読みながら、まるで幸せのお裾分けを貰ったみたいにふくふくとした気分になってくるのは何故なのだろうか。
共に食事をするのも大切だけど、それだけが家族じゃないんだよね。

わりと今風の表紙、と思ったら、新装版で4月に発売されたばかり。
「ハイ・ミスというものは、意地が悪いものだ。意地が悪くなくてハイ・ミス商売張っていけるか」というマリ子の恋愛話も、もちろん楽しめます。
帯には、西加奈子の言葉がありました。
「田辺さんの手にかかると、日常はこんなにも滋味深い」
同時発売の『夕ごはんたべた?』も、ぜひ読みたいなぁ。

『朝ごはんぬき?』(新潮文庫)1976年に出版された小説だ。
裏表紙の紹介文に「ハイ・ミス」という言葉が使われていることからも、最近かかれたものではないと判る。主人公はそのハイ・ミス。31歳で未婚の明田マリ子。ハイ・ミスという言葉も聞かなくなったが、31歳をハイ・ミスと呼ぶこと自体、今ではあり得ないんじゃないか、などと思いつつ読み始めたのだが、ページを捲る指は止まらなかった。ユーモア小説と言われるだけのことはあり、おもしろいのだ。
失恋して会社を辞めたマリ子は、女流作家秋本えりか(本名、土井ヨシ乃)の家で住み込みで働くことになった。お手伝い兼、秘書兼、イヌの散歩係だ。その家族の様子が、何ともおもしろい。
売れっ子作家のえりかは、締め切りぎりぎりにならないと原稿をかきはじめず、編集者からの電話には「いないと、言って!」と怒鳴る。えりかの夫は、そんな妻にも慣れていて、常にのんびりと傍観。放って熟睡し、マリ子に「鉄人・ねむり犀(さい)」とあだ名をつけられる。女子高生の娘、さゆりちゃんは、反抗はしないが大人とは関わりたくないと思っている様子。カップヌードル党。3人の家族は、一緒に食事をしない。マリ子は、そんな3人に何やら納得しない思いを抱きつつも、自分の仕事をきちんとこなすのだ。
以下、ねむり犀、土井氏が、帰りが遅くなったさゆりちゃんを叱るシーン。
「困った子やな。そう外食ばかりしてはあかん。子供はちゃんと、家でモノをたべる」土井氏は嘆息して「何を食べた」と好奇心にみちて聞いた。
この人、食べ物の話をするときは、とみに生き生きする。
「豚珍軒のごもく焼きそば …… 」
と、さゆりちゃんは悪事を働いたごとく、うなだれる。
「ごもく焼きそばか、あれは量が多いばかりでまずい。豚珍軒はラーメンのおつゆがうまいのです。塩味ラーメン食べればよかったのに、なんで、まずうて高うて量ばかり多いごもく焼きそばなんか、食べるのや!」
さゆりちゃんは泣きべそをかいて、もじもじする。
「もし焼きそばなら、向かいの天珍楼にすればよかったのに!」
ここまで的を外し説教できる父親って、じつにすごいと思ってしまった。
そして、蒸発(?)した土井氏を迎えた、えりか氏の台詞がまた、すごい。
「夫というものは、家に帰ればいつもいるもの、妻にさからわず、妻の邪魔をせず、要るときだけ、前へ出てくるもの、勝手にかげで自由行動することは許さん! 離婚の、蒸発の、とそういう自由も許さん …… 」
こんな家族、あり得ないと呆れつつも、読みながら、まるで幸せのお裾分けを貰ったみたいにふくふくとした気分になってくるのは何故なのだろうか。
共に食事をするのも大切だけど、それだけが家族じゃないんだよね。
わりと今風の表紙、と思ったら、新装版で4月に発売されたばかり。
「ハイ・ミスというものは、意地が悪いものだ。意地が悪くなくてハイ・ミス商売張っていけるか」というマリ子の恋愛話も、もちろん楽しめます。
帯には、西加奈子の言葉がありました。
「田辺さんの手にかかると、日常はこんなにも滋味深い」
同時発売の『夕ごはんたべた?』も、ぜひ読みたいなぁ。
『嵐のピクニック』
本谷有希子の短編集『嵐のピクニック』(講談社文庫)を読んだ。
本屋での衝動買いは珍しいことではないが、帯の文句に魅かれることは、わたし的にはとても珍しい。
「奇妙な味」の短編が発想と形式の見本帳というほどにも、繰り返される。
― 大江健三郎 と、帯にはかかれていた。
薄い文庫であり、13の短編とも掌編とも言える小説を収めているところにも魅かれた。裏表紙の紹介文に、「狂気」「妄想」「ブラック」「奇想天外」などの言葉が並んでいるのにも、わくわくした。
そしてわたしは、読み始めてすぐ、そこに言葉を追加した。「呆然」
2話目『私は名前で呼んでいる』は、会議中、カーテンの膨らみが気になってどうしようもなくなる女性部長を描いた掌編。以下本文から。
なんでそんなにも思わせぶりに膨らんでいるの? さっきは弱気になったけど、私はあなたたちのことを「気のせい」なんて認めない。そうやって、さも何かいる雰囲気で膨らんで、私だけじゃない、今まで世界中の人たちをどれだけ動揺させてきたのよ。誰かいるの? いないの? はっきりしなさいよ。
やがて彼女は会議室を飛び出し、走りだした。そして、見上げたビルの窓に、自分を見下ろす誰かを見つけたのだった。
大江健三郎賞を受賞したときの選評がラストに収められているのだが、そこで大江はかいている。「フクシマ3.11以来」と前置き「まったくの久しぶりで、希望の気配のある小説を読んだ思いがしました」
これを読み、えっ、そうなの? と思ったが、この短編集を読み終えると、確かに気持ちが明るくなっていた。ヒトって、実はどうでもいいことを真剣に思い悩み生きているのかも知れないと、すとんと腑に落ち肩の力が抜けたのだ。

本谷有希子(もとやゆきこ)1979年生まれ。
2000年「劇団、本谷有希子」を旗揚げし、主宰として作・演出を手がける。本書で、第7回大江健三郎賞を、『自分を好きになる方法』(講談社)で、第27回三島由紀夫賞を受賞。

短編タイトルの、この絶妙微妙な傾き加減にも奇妙さが表れています。

ここまでくると、はっきりと奇妙です。まっすぐにはなれない悲しさ?
それは、喜びでもあるのかな。または、まっすぐにはならないという決心か。

本屋での衝動買いは珍しいことではないが、帯の文句に魅かれることは、わたし的にはとても珍しい。
「奇妙な味」の短編が発想と形式の見本帳というほどにも、繰り返される。
― 大江健三郎 と、帯にはかかれていた。
薄い文庫であり、13の短編とも掌編とも言える小説を収めているところにも魅かれた。裏表紙の紹介文に、「狂気」「妄想」「ブラック」「奇想天外」などの言葉が並んでいるのにも、わくわくした。
そしてわたしは、読み始めてすぐ、そこに言葉を追加した。「呆然」
2話目『私は名前で呼んでいる』は、会議中、カーテンの膨らみが気になってどうしようもなくなる女性部長を描いた掌編。以下本文から。
なんでそんなにも思わせぶりに膨らんでいるの? さっきは弱気になったけど、私はあなたたちのことを「気のせい」なんて認めない。そうやって、さも何かいる雰囲気で膨らんで、私だけじゃない、今まで世界中の人たちをどれだけ動揺させてきたのよ。誰かいるの? いないの? はっきりしなさいよ。
やがて彼女は会議室を飛び出し、走りだした。そして、見上げたビルの窓に、自分を見下ろす誰かを見つけたのだった。
大江健三郎賞を受賞したときの選評がラストに収められているのだが、そこで大江はかいている。「フクシマ3.11以来」と前置き「まったくの久しぶりで、希望の気配のある小説を読んだ思いがしました」
これを読み、えっ、そうなの? と思ったが、この短編集を読み終えると、確かに気持ちが明るくなっていた。ヒトって、実はどうでもいいことを真剣に思い悩み生きているのかも知れないと、すとんと腑に落ち肩の力が抜けたのだ。
本谷有希子(もとやゆきこ)1979年生まれ。
2000年「劇団、本谷有希子」を旗揚げし、主宰として作・演出を手がける。本書で、第7回大江健三郎賞を、『自分を好きになる方法』(講談社)で、第27回三島由紀夫賞を受賞。
短編タイトルの、この絶妙微妙な傾き加減にも奇妙さが表れています。
ここまでくると、はっきりと奇妙です。まっすぐにはなれない悲しさ?
それは、喜びでもあるのかな。または、まっすぐにはならないという決心か。
『夜と妻と洗剤』
江國香織の小説のなかで、とても好きな掌編がある。
『江國香織とっておき作品集』(マガジンハウス)に収められた『夜と妻と洗剤』だ。この小説は、こんなふうに始まる。
妻が、僕と別れたいと言った。私たち、話し合わなきゃ、と。
夜の十時をすぎていた。僕は疲れていた。僕たちは結婚して五年目で、子供はいない。
気がつかないふりをして暮らすことはできるわ、と、妻は言った。でも、気がつかないふりをしても、それはなくなりはしないのよ、と。
僕が返事をせずにテレビをみていると、妻はテレビを消してしまった。何に気がつかないふりをして暮らすのか、何がなくなりはしないのか、僕にはさっぱりわからない。いつものことだ。
文字数にすると、ここまでで200字と少し。ラストまで行っても多分この5倍くらいにしかならないだろうから、約1000字。原稿用紙換算にして3枚に満たない掌編中の掌編だ。
主人公は、妻のペティキュアが剥がれかけているのに気づき、除光液を切らしていてイライラしているのだろうと推測する。だが、そうではなかった。
「私が言っているのは、そういうことじゃないの」
主人公は、さらに足りないものを言い並べていく。
「洗剤は? 牛乳は? ダイエットペプシは?」
それは、コンビニに売っているモノばかりだ。しかし、妻はため息をつく。
「私が言おうとしていることは、そういうものとは関係がないのよ」
だが主人公は、妻を振り切ってコンビニに向かう。そして洗剤やら牛乳やらダイエットペプシやらを大量に買い込んできて、妻は呆れて笑いだすのだ。
ストーリーは以上だ。何が好きかと言えば、男と女が求めているモノの違いと、永遠にすれ違っていく滑稽さが、この短い文字の羅列のなかに、多すぎず少なすぎず描かれているのが、いい。この小説を読むと、永遠に続く平行線も、笑って歩けるような気分になるのだ。

エッセイ集『やわらかなレタス』(文芸春秋)と一緒に。

銅版画家、山本容子の、不思議な雰囲気の絵がついていました。

『江國香織とっておき作品集』(マガジンハウス)に収められた『夜と妻と洗剤』だ。この小説は、こんなふうに始まる。
妻が、僕と別れたいと言った。私たち、話し合わなきゃ、と。
夜の十時をすぎていた。僕は疲れていた。僕たちは結婚して五年目で、子供はいない。
気がつかないふりをして暮らすことはできるわ、と、妻は言った。でも、気がつかないふりをしても、それはなくなりはしないのよ、と。
僕が返事をせずにテレビをみていると、妻はテレビを消してしまった。何に気がつかないふりをして暮らすのか、何がなくなりはしないのか、僕にはさっぱりわからない。いつものことだ。
文字数にすると、ここまでで200字と少し。ラストまで行っても多分この5倍くらいにしかならないだろうから、約1000字。原稿用紙換算にして3枚に満たない掌編中の掌編だ。
主人公は、妻のペティキュアが剥がれかけているのに気づき、除光液を切らしていてイライラしているのだろうと推測する。だが、そうではなかった。
「私が言っているのは、そういうことじゃないの」
主人公は、さらに足りないものを言い並べていく。
「洗剤は? 牛乳は? ダイエットペプシは?」
それは、コンビニに売っているモノばかりだ。しかし、妻はため息をつく。
「私が言おうとしていることは、そういうものとは関係がないのよ」
だが主人公は、妻を振り切ってコンビニに向かう。そして洗剤やら牛乳やらダイエットペプシやらを大量に買い込んできて、妻は呆れて笑いだすのだ。
ストーリーは以上だ。何が好きかと言えば、男と女が求めているモノの違いと、永遠にすれ違っていく滑稽さが、この短い文字の羅列のなかに、多すぎず少なすぎず描かれているのが、いい。この小説を読むと、永遠に続く平行線も、笑って歩けるような気分になるのだ。
エッセイ集『やわらかなレタス』(文芸春秋)と一緒に。
銅版画家、山本容子の、不思議な雰囲気の絵がついていました。
『サラバ!』
西加奈子の『サラバ!』(小学館)を、読んだ。
冒頭文から、物語のなかにひき込まれた。読みながら、わくわくした。
そして、自分の読書ポリシーは間違っていなかったと叫びたくなった。テーマも、教訓もいらない。本とは、まずは面白くあるべきものなのだ。
「面白くない本は、読まなくていい」「読書は、娯楽だ」
何度も子ども達に、言って聞かせたっけ。そして彼らは、わたしよりも遥かに多くの本を読む大人になった。
もし子ども達に読書の楽しさを伝えたいのなら「国語力が伸びるよ」「ためになるよ」などとは口が裂けても言わず、ぜひ「読書は、娯楽だ」と言い続けてほしい。どうしても読んでほしい本がある場合には「この本は、子どもが読むには面白すぎるから絶対に読んではいけない」と言い置き、鍵つきの引き出しに仕舞うのもいいかも知れない。(そして、感想は聞かない。これが基本だ)
しかし、読み終えて呆然とした。『サラバ!』が描くものは、そのテーマがしっかりと、もう地球をがんじがらめにするほどに強く根をはった骨太のものなのだった。二の次だと思っていたテーマ性は、面白さに上回るほどインパクトの強いものだったのだ。
『サラバ!』の語り手は、ひとりである。圷歩(あくつあゆむ)が生まれた時から、37歳の「今」に至るまでを、歩が語る。その歩の物語の主要登場人物を、文中の言葉で紹介していこうと思う。
まずは母、奈緒子。歩を産んで退院した時の写真から。
「ピンボケしているので、はっきりと確認出来ないが、母は唇を真っ赤に塗っているようだったし、つまり彼女は、母になっても自分のスタイルを変えないタイプの人間だったのだ。短いスカートを穿きたいと思えば穿いたし、それに合うヒールの靴を、ぺたんこの靴に履きかえることもなかった」
そして姉、貴子。長らく母と対立してきたことについての彼女の言葉。
「母親って、お腹を痛めて産んだ子を愛するって言うけど、私はそうじゃないと思うわ。お腹を痛めれば痛めるほど、苦しめば苦しむほど、その痛みや苦しみを、子供で取り返そうとすんのよ。分かる? あんたはいいわよ、麻酔してなーんにも分からない間に、するっと生まれてきたんだから、何も取り戻す必要ないの。ほら、あんたって、全然期待されてないじゃない? でも私は、覚えてないから迷惑な話だけど、だいぶあの人を苦しめたわけでしょ、だからあの人は、私から何か取り戻したいのよ。あんなに苦しんだんだから、せめて可愛い子であってほしい、とか、優秀であってほしい、とか。ご希望に添えなくて、申し訳ないけどね」
そして父、憲太郎。圷家で、磐石な態勢で長きに渡り顕在していたモノ。
それは「母vs姉、そして、その間をオロオロと揺れ動く父」なのだった。
そんな家族のなかにいて、歩は空気を読む子どもに育っていく。
幼稚園時代に流行ったクレヨンを取り換える遊び(一番好きな男子には「青」を、一番好きな女子には「ピンク」を渡す)についての記述。
「僕のクレヨン箱は非常に鮮やかだった。数本の青とたくさんの水色、黄緑色、緑などの美しい色たち。僕は決して一番人気の園児ではなかったが、2番か3番につけていた。そしてもしかしたら、そのほうがアンチもいる1番の〈すなが れん〉より優れていたのではなかろうか」
『サラバ!』は、そんな周囲の空気を常に読みつつ成長した歩と、破天荒な姉、幸せになろうとし続けた母と幸せになることを拒んだ父の物語である。

表紙は、著者、西加奈子による16枚の絵を分割し組み合わせたものです。
圷家が家族4人で過ごしたイランやエジプトの風景も。それはすなわち西加奈子が生まれたイランや、幼少期を過ごしたエジプトの風景なのですが。
小学館のサイトから、その16枚の絵を見ることができます。

冒頭文から、物語のなかにひき込まれた。読みながら、わくわくした。
そして、自分の読書ポリシーは間違っていなかったと叫びたくなった。テーマも、教訓もいらない。本とは、まずは面白くあるべきものなのだ。
「面白くない本は、読まなくていい」「読書は、娯楽だ」
何度も子ども達に、言って聞かせたっけ。そして彼らは、わたしよりも遥かに多くの本を読む大人になった。
もし子ども達に読書の楽しさを伝えたいのなら「国語力が伸びるよ」「ためになるよ」などとは口が裂けても言わず、ぜひ「読書は、娯楽だ」と言い続けてほしい。どうしても読んでほしい本がある場合には「この本は、子どもが読むには面白すぎるから絶対に読んではいけない」と言い置き、鍵つきの引き出しに仕舞うのもいいかも知れない。(そして、感想は聞かない。これが基本だ)
しかし、読み終えて呆然とした。『サラバ!』が描くものは、そのテーマがしっかりと、もう地球をがんじがらめにするほどに強く根をはった骨太のものなのだった。二の次だと思っていたテーマ性は、面白さに上回るほどインパクトの強いものだったのだ。
『サラバ!』の語り手は、ひとりである。圷歩(あくつあゆむ)が生まれた時から、37歳の「今」に至るまでを、歩が語る。その歩の物語の主要登場人物を、文中の言葉で紹介していこうと思う。
まずは母、奈緒子。歩を産んで退院した時の写真から。
「ピンボケしているので、はっきりと確認出来ないが、母は唇を真っ赤に塗っているようだったし、つまり彼女は、母になっても自分のスタイルを変えないタイプの人間だったのだ。短いスカートを穿きたいと思えば穿いたし、それに合うヒールの靴を、ぺたんこの靴に履きかえることもなかった」
そして姉、貴子。長らく母と対立してきたことについての彼女の言葉。
「母親って、お腹を痛めて産んだ子を愛するって言うけど、私はそうじゃないと思うわ。お腹を痛めれば痛めるほど、苦しめば苦しむほど、その痛みや苦しみを、子供で取り返そうとすんのよ。分かる? あんたはいいわよ、麻酔してなーんにも分からない間に、するっと生まれてきたんだから、何も取り戻す必要ないの。ほら、あんたって、全然期待されてないじゃない? でも私は、覚えてないから迷惑な話だけど、だいぶあの人を苦しめたわけでしょ、だからあの人は、私から何か取り戻したいのよ。あんなに苦しんだんだから、せめて可愛い子であってほしい、とか、優秀であってほしい、とか。ご希望に添えなくて、申し訳ないけどね」
そして父、憲太郎。圷家で、磐石な態勢で長きに渡り顕在していたモノ。
それは「母vs姉、そして、その間をオロオロと揺れ動く父」なのだった。
そんな家族のなかにいて、歩は空気を読む子どもに育っていく。
幼稚園時代に流行ったクレヨンを取り換える遊び(一番好きな男子には「青」を、一番好きな女子には「ピンク」を渡す)についての記述。
「僕のクレヨン箱は非常に鮮やかだった。数本の青とたくさんの水色、黄緑色、緑などの美しい色たち。僕は決して一番人気の園児ではなかったが、2番か3番につけていた。そしてもしかしたら、そのほうがアンチもいる1番の〈すなが れん〉より優れていたのではなかろうか」
『サラバ!』は、そんな周囲の空気を常に読みつつ成長した歩と、破天荒な姉、幸せになろうとし続けた母と幸せになることを拒んだ父の物語である。
表紙は、著者、西加奈子による16枚の絵を分割し組み合わせたものです。
圷家が家族4人で過ごしたイランやエジプトの風景も。それはすなわち西加奈子が生まれたイランや、幼少期を過ごしたエジプトの風景なのですが。
小学館のサイトから、その16枚の絵を見ることができます。
『サラバ!』予告編
『鹿の王』を読み終えてから、面白い本に集中しすぎたときに起こる脱力感が身体じゅうを支配し、しばらく本を手にとれなかった。
気分転換に「このミス大賞」をとったミステリーを読むには読んだが楽しめず、脱力感は深まるばかり。これはもう、どーんと大物に挑むしかないと『サラバ!』(小学館)を読むことに決めた。
分厚い上下2冊。直木賞受賞作にして、本屋大賞第2位をとった小説だ。西加奈子は5冊ほど読んでいるので、相性が悪くないことも知っている。
しかし、読もうと決めた途端『サラバ!』は、わたしから逃げていった。
ベストセラーが並んだ新宿駅ナカの本屋では、売り切れ。あずさに乗り帰って来た甲府駅ビルの本屋で、やれやれと手にしてレジに並ぶも、前に並んでいた男性がややこしいことを店員に言っていて、電車の時間となりあきらめた。その夜、夫を迎えに出たついでに寄った隣町の本屋は、タッチの差で閉店時間。翌日買いに走るも、ふたたび売り切れていた。
『サラバ!』は「サラバー」と駄洒落でも言っているかの如く、するりとわたしをかわしていく。「縁」というものの不思議は、人とだけではなく、モノとの間にもあるのだということを思わずにはいられなかった。
という訳で、そこであきらめることも考えたが、考えるほどにあきらめきれず、昨日ようやく『サラバ!』は、わたしの手もとにやって来た。お隣の、そのまた隣りの市にあるショッピングモールの本屋まで車を走らせて買ったのだ。本屋で見つけ、手にした時には震えた。このチャンスを逃したら一生読めないかもしれないと、本気で考えている自分がいた。
普段は(?)フラれた相手をしつこく追いかけるようなことはしないのだが、今回に限り、見逃してほしい。追いかければ、手にすることができる「縁」もまた、存在するのである。

「僕はこの世界に、左足から登場した。母の体外にそっと、本当にそっと左足を突き出して、ついでおずおずと、右足を出したそうだ。両足を出してから、速やかに全身を現すことはなかった。しばらくその状態でいたのは、おそらく、新しい空気との距離を、測っていたのだろう」冒頭文です。わくわく。

気分転換に「このミス大賞」をとったミステリーを読むには読んだが楽しめず、脱力感は深まるばかり。これはもう、どーんと大物に挑むしかないと『サラバ!』(小学館)を読むことに決めた。
分厚い上下2冊。直木賞受賞作にして、本屋大賞第2位をとった小説だ。西加奈子は5冊ほど読んでいるので、相性が悪くないことも知っている。
しかし、読もうと決めた途端『サラバ!』は、わたしから逃げていった。
ベストセラーが並んだ新宿駅ナカの本屋では、売り切れ。あずさに乗り帰って来た甲府駅ビルの本屋で、やれやれと手にしてレジに並ぶも、前に並んでいた男性がややこしいことを店員に言っていて、電車の時間となりあきらめた。その夜、夫を迎えに出たついでに寄った隣町の本屋は、タッチの差で閉店時間。翌日買いに走るも、ふたたび売り切れていた。
『サラバ!』は「サラバー」と駄洒落でも言っているかの如く、するりとわたしをかわしていく。「縁」というものの不思議は、人とだけではなく、モノとの間にもあるのだということを思わずにはいられなかった。
という訳で、そこであきらめることも考えたが、考えるほどにあきらめきれず、昨日ようやく『サラバ!』は、わたしの手もとにやって来た。お隣の、そのまた隣りの市にあるショッピングモールの本屋まで車を走らせて買ったのだ。本屋で見つけ、手にした時には震えた。このチャンスを逃したら一生読めないかもしれないと、本気で考えている自分がいた。
普段は(?)フラれた相手をしつこく追いかけるようなことはしないのだが、今回に限り、見逃してほしい。追いかければ、手にすることができる「縁」もまた、存在するのである。
「僕はこの世界に、左足から登場した。母の体外にそっと、本当にそっと左足を突き出して、ついでおずおずと、右足を出したそうだ。両足を出してから、速やかに全身を現すことはなかった。しばらくその状態でいたのは、おそらく、新しい空気との距離を、測っていたのだろう」冒頭文です。わくわく。
『鹿の王』
今年2015年の本屋大賞を取った上橋菜穂子の『鹿の王』(角川書店)を読んだ。ノミネートされた時から読みたいと思っていた。彼女の本はほとんど読んでいて、楽しい読書タイムになることは判っていたからだ。読み始めてすぐに、ぐいっと物語世界のなかへひき込んでくれる。それが上橋菜穂子なのだ。
物語は、架空の世界が舞台。畑を耕し狩りをして、釜戸で料理をし、刀や弓で戦う人々が生きる時代。
主人公は、闘い破れて奴隷となり岩塩鉱で働かされているもと戦士、ヴァンと、帝国支配下で働く若き優秀な医師、ホッサル。ふたりを交互に追いつつ、ストーリーは進んでいく。
突然、山犬のような獣に襲われ、岩塩鉱は奴隷も見張りの兵士も全滅した。そのなかで生き残ったのがヴァンと1歳の女の子、ユナだった。ヴァンはユナを連れ、逃亡する。一方、ホッサルは、岩塩鉱で死んだ人々の死因を探る。獣に噛まれ死病に感染した疑いが強く、ホッサルの祖先が国を捨てた原因となる「伝説の病」再発かと考えたのだ。しかし、逃亡したヴァンもユナも獣に噛まれていた。生き残った者と死んだ者。その違いは何か。ヴァンとホッサル。会ったことのないふたりだったが、離れた場所で、同じ疑問を抱えていた。
ヴァンの故郷トガ山地では、馬でも牛でもなく飛鹿(ピュイカ)に乗る。
以下、下巻、ヴァンが初対面のホッサルに、故郷のしきたりを語るシーン。
「飛鹿の群れの中には、群れが危機に陥ったとき、己の命を張って群れを逃がす鹿が現れるのです。長でもなく、仔も持たぬ鹿であっても、危機に逸早く気づき、我が身を賭して群れをたすける鹿が。
たいていは、かつて頑健であった牡で、いまはもう盛りを過ぎ、しかしなお敵と戦う力を充分に残しているようなものが、そういうことをします。
私たちは、こういう鹿を尊び<鹿の王>と呼んでいます。群れを支配する者、という意味ではなく、本当の意味で群れの存続を支える尊むべき者として」
ヴァンは、妻と息子を病で亡くしていて、戦士になったのも死ぬためだった。そんな彼の心に灯りを燈したのは、ユナだ。ユナがいることで物語の色が全く違うものになっている。以下、下巻、さらわれたユナを追い野宿するシーン。
「ユナが、な」ヴァンは口を開いた。
「木割れの音を聞くたびに、ぴょん、と跳ねるんだ」
初めて木割れの音を聞いたとき、驚いて飛びあがったのを見たオゥマたちが、大笑いしたのがうれしかったらしい。木割れの音がするたびに、驚いたふりをして、兎のように跳び上がるようになったのだ。それがまた、毎回毎回、様々工夫を凝らした迫真の演技なので、今度はどんな風に跳び上がるかと、見ている方も結構楽しみだった。
そんなことを話すと、サエは小さく声をたてて笑った。物静かなこの人が笑うと、なんとなく、小さな褒美をもらったような気分になる。
ユナが微笑ましく、それを思い口元を緩めるヴァンの愛が伝わって来て、こちらも思わず笑顔になった。
重苦しい悩み事を抱えながら、長い人生、時間を積み重ねていけるのも、そんな一瞬があるからこそだ。小さな瞬間に光を見出だすことの大切さは、ファンタジーと呼ばれる架空世界でも、今立っている現実でも変わらないのだということを、ページをめくりつつ指先に感じた。
飛鹿の駆ける世界を、堪能した夜だった。

上巻には、飛鹿。下巻には、キンマの犬が描かれています。

カバーをとった装幀です。やわらかなブルーとオレンジ。

中表紙も、お見せしましょう。栞の色も、もちろん同系色。


物語は、架空の世界が舞台。畑を耕し狩りをして、釜戸で料理をし、刀や弓で戦う人々が生きる時代。
主人公は、闘い破れて奴隷となり岩塩鉱で働かされているもと戦士、ヴァンと、帝国支配下で働く若き優秀な医師、ホッサル。ふたりを交互に追いつつ、ストーリーは進んでいく。
突然、山犬のような獣に襲われ、岩塩鉱は奴隷も見張りの兵士も全滅した。そのなかで生き残ったのがヴァンと1歳の女の子、ユナだった。ヴァンはユナを連れ、逃亡する。一方、ホッサルは、岩塩鉱で死んだ人々の死因を探る。獣に噛まれ死病に感染した疑いが強く、ホッサルの祖先が国を捨てた原因となる「伝説の病」再発かと考えたのだ。しかし、逃亡したヴァンもユナも獣に噛まれていた。生き残った者と死んだ者。その違いは何か。ヴァンとホッサル。会ったことのないふたりだったが、離れた場所で、同じ疑問を抱えていた。
ヴァンの故郷トガ山地では、馬でも牛でもなく飛鹿(ピュイカ)に乗る。
以下、下巻、ヴァンが初対面のホッサルに、故郷のしきたりを語るシーン。
「飛鹿の群れの中には、群れが危機に陥ったとき、己の命を張って群れを逃がす鹿が現れるのです。長でもなく、仔も持たぬ鹿であっても、危機に逸早く気づき、我が身を賭して群れをたすける鹿が。
たいていは、かつて頑健であった牡で、いまはもう盛りを過ぎ、しかしなお敵と戦う力を充分に残しているようなものが、そういうことをします。
私たちは、こういう鹿を尊び<鹿の王>と呼んでいます。群れを支配する者、という意味ではなく、本当の意味で群れの存続を支える尊むべき者として」
ヴァンは、妻と息子を病で亡くしていて、戦士になったのも死ぬためだった。そんな彼の心に灯りを燈したのは、ユナだ。ユナがいることで物語の色が全く違うものになっている。以下、下巻、さらわれたユナを追い野宿するシーン。
「ユナが、な」ヴァンは口を開いた。
「木割れの音を聞くたびに、ぴょん、と跳ねるんだ」
初めて木割れの音を聞いたとき、驚いて飛びあがったのを見たオゥマたちが、大笑いしたのがうれしかったらしい。木割れの音がするたびに、驚いたふりをして、兎のように跳び上がるようになったのだ。それがまた、毎回毎回、様々工夫を凝らした迫真の演技なので、今度はどんな風に跳び上がるかと、見ている方も結構楽しみだった。
そんなことを話すと、サエは小さく声をたてて笑った。物静かなこの人が笑うと、なんとなく、小さな褒美をもらったような気分になる。
ユナが微笑ましく、それを思い口元を緩めるヴァンの愛が伝わって来て、こちらも思わず笑顔になった。
重苦しい悩み事を抱えながら、長い人生、時間を積み重ねていけるのも、そんな一瞬があるからこそだ。小さな瞬間に光を見出だすことの大切さは、ファンタジーと呼ばれる架空世界でも、今立っている現実でも変わらないのだということを、ページをめくりつつ指先に感じた。
飛鹿の駆ける世界を、堪能した夜だった。
上巻には、飛鹿。下巻には、キンマの犬が描かれています。
カバーをとった装幀です。やわらかなブルーとオレンジ。
中表紙も、お見せしましょう。栞の色も、もちろん同系色。
『白河夜船』
睡眠を見直そうかなと、昨日かいたばかりだが、偶然にも読み始めた小説が「眠り三部作」と呼ばれる短編集だった。
吉本ばなな『白河夜船』(新潮文庫)は、表題作の他『夜と夜の旅人』『ある体験』の3つの短編が収められた薄い文庫で、どれも「眠り」と「死」のかかわりを描いている。『白河夜船』は、眠りに憑りつかれた女性の物語だ。
寺子は親友だったしおりの死後、仕事も辞め、眠ってばかりの生活を送っていた。恋人には、事故で植物人間になった妻がいて、彼女は寺子よりも深く眠っている。しかし寺子は、眠りをストレートに受け入れている訳ではなく、抗う気持ちも強く持っていた。以下、本文から。
「今って、朝の五時なんだわ」と口に出した自分の声が乾いていた。
私は心底、恐かった。いったい、時計は幾回りしたのか。今は、何月何日なのか。夢中で部屋を出て階段を降りて行って、ポストに入っている新聞を広げてみた。大丈夫。一晩眠っただけだった、と私は安心した。しかし、それにしても尋常ではない時間を眠り続けたのは確かだった。体中が少し調子を狂わせているのがわかる。なんだか目まいがした。夜明けの青が街中に蔓延して、街灯の光が透明だった。私は部屋に戻るのが本当にこわくて仕方がなかった。きっとまた、眠ってしまう ― いっそ、やけくそになって眠ってしまおうかとも思った。もう、行き場がないような気さえした。
私は、なんとなくそのまま外へ歩いて行った。
寺子が、うつらうつらしながら歩き座り込んだ公園のベンチで会った少女のなかには、しおりがいた。少女の身体を借り、寺子に忠告しにきたのだ。
「私にとても近いところにいるから、会えてしまったのかもしれない」と。
眠っている間、意識が何処へ行っているのか。「死」と近い場所へ行っているのではないか。「死」とは、深く深く眠ることなのだろうか。
眠りも死後も、解明できないものだからこそ、そんな風に考えるのかも知れないが、もしそれが真実だったらと、読み終えてぼんやりと、考えた。
久々にジャケ買いした、新潮社のお洒落な文庫です。
「白河夜船(しらかわよふね)」とは、何も気づかないほどぐっすり眠ることを言うのだとか。映画『白河夜船』は、4月25日公開。


吉本ばなな『白河夜船』(新潮文庫)は、表題作の他『夜と夜の旅人』『ある体験』の3つの短編が収められた薄い文庫で、どれも「眠り」と「死」のかかわりを描いている。『白河夜船』は、眠りに憑りつかれた女性の物語だ。
寺子は親友だったしおりの死後、仕事も辞め、眠ってばかりの生活を送っていた。恋人には、事故で植物人間になった妻がいて、彼女は寺子よりも深く眠っている。しかし寺子は、眠りをストレートに受け入れている訳ではなく、抗う気持ちも強く持っていた。以下、本文から。
「今って、朝の五時なんだわ」と口に出した自分の声が乾いていた。
私は心底、恐かった。いったい、時計は幾回りしたのか。今は、何月何日なのか。夢中で部屋を出て階段を降りて行って、ポストに入っている新聞を広げてみた。大丈夫。一晩眠っただけだった、と私は安心した。しかし、それにしても尋常ではない時間を眠り続けたのは確かだった。体中が少し調子を狂わせているのがわかる。なんだか目まいがした。夜明けの青が街中に蔓延して、街灯の光が透明だった。私は部屋に戻るのが本当にこわくて仕方がなかった。きっとまた、眠ってしまう ― いっそ、やけくそになって眠ってしまおうかとも思った。もう、行き場がないような気さえした。
私は、なんとなくそのまま外へ歩いて行った。
寺子が、うつらうつらしながら歩き座り込んだ公園のベンチで会った少女のなかには、しおりがいた。少女の身体を借り、寺子に忠告しにきたのだ。
「私にとても近いところにいるから、会えてしまったのかもしれない」と。
眠っている間、意識が何処へ行っているのか。「死」と近い場所へ行っているのではないか。「死」とは、深く深く眠ることなのだろうか。
眠りも死後も、解明できないものだからこそ、そんな風に考えるのかも知れないが、もしそれが真実だったらと、読み終えてぼんやりと、考えた。
久々にジャケ買いした、新潮社のお洒落な文庫です。
「白河夜船(しらかわよふね)」とは、何も気づかないほどぐっすり眠ることを言うのだとか。映画『白河夜船』は、4月25日公開。
『ボクの町』
引き続き、乃南アサを読んでいる。昨日『ボクの町』(新潮文庫)を、読み終えた。交番で巡査見習いをする青年の物語である。
名は、高木聖大(せいだい)23歳。警察官を目指したのは、フラれた彼女を見返してやりたかったから。耳にはピアス、警察手帳にはその彼女と撮ったプリクラ。汗水たらして働くのなんか、柄じゃないと自分では思っている。先輩警官達にも、物怖じしないどころか生意気な態度さえとってしまうのは、じつは馬鹿正直で気が短く、思っていることがすぐに顔に出てしまうからだ。
以下、110番マニアの度重なる通報に爆発するシーン。
「ふざけんな!」思わず班長を押しのけて怒鳴っていた。瞬間、宮永班長が肩を掴んだが、もう止められなかった。
「俺らはなあ、ソバや寿司の出前じゃねぇんだよ!」
真っ白かった北川の顔が、見る見るうちに赤く染まっていく。腫れぼったい瞼の下の細い目が、落ち着きなく左右に揺れた。
「てめえの暇つぶしの相手なんか、してられるか! 淋しいんだったら、友達でも彼女でも、自分で探せ! それも出来ねえんだったら、お前なんか田舎に帰れ!」
「い、いいのかよ、善良な市民に、そんなこと言って。いいと思ってるのか」
「てめえなんか、善良でも何でもねえよ。生っちろい、ウジ虫野郎じゃねぇか。こっちは毎日汗だくになってかけずり回ってるっていうのに、てめえは働きもしねえで、何様のつもりなんだ!」
そんな聖大も、いや、そんな聖大だからこそ、自分がこのまま警察官を目指すべきなのか迷い、失敗に落ち込み、優秀な同期の三浦をやっかみ、やってられねぇと自棄になり、見習い期間のあいだ、悩み続けていた。
そんなとき、連続放火犯と対峙した三浦が大怪我を負う。聖大は、気持ちに迷いを抱えたまま、ひたすら犯人を追うしかなかった。
印象に残ったのは「人間なんて、汚いのが当たり前だ」という先輩刑事の言葉だった。人間誰もが持っている、その汚い部分を目の当たりにし、人間が嫌いになったり、人が信じられなくなったりしながら、それでも続けていこうと思えるのは「人間って、まんざら捨てたものじゃない」と思える瞬間があるからだと、まだ年若き、ほんの少しだけ先輩の刑事が、迷い悩む聖大に語るのだ。

新米巡査高木聖大シリーズは、今のところ2冊。次は『駆けこみ交番』です。
少し成長した聖大くんが登場する『いつか陽のあたる場所で』もおススメ。

名は、高木聖大(せいだい)23歳。警察官を目指したのは、フラれた彼女を見返してやりたかったから。耳にはピアス、警察手帳にはその彼女と撮ったプリクラ。汗水たらして働くのなんか、柄じゃないと自分では思っている。先輩警官達にも、物怖じしないどころか生意気な態度さえとってしまうのは、じつは馬鹿正直で気が短く、思っていることがすぐに顔に出てしまうからだ。
以下、110番マニアの度重なる通報に爆発するシーン。
「ふざけんな!」思わず班長を押しのけて怒鳴っていた。瞬間、宮永班長が肩を掴んだが、もう止められなかった。
「俺らはなあ、ソバや寿司の出前じゃねぇんだよ!」
真っ白かった北川の顔が、見る見るうちに赤く染まっていく。腫れぼったい瞼の下の細い目が、落ち着きなく左右に揺れた。
「てめえの暇つぶしの相手なんか、してられるか! 淋しいんだったら、友達でも彼女でも、自分で探せ! それも出来ねえんだったら、お前なんか田舎に帰れ!」
「い、いいのかよ、善良な市民に、そんなこと言って。いいと思ってるのか」
「てめえなんか、善良でも何でもねえよ。生っちろい、ウジ虫野郎じゃねぇか。こっちは毎日汗だくになってかけずり回ってるっていうのに、てめえは働きもしねえで、何様のつもりなんだ!」
そんな聖大も、いや、そんな聖大だからこそ、自分がこのまま警察官を目指すべきなのか迷い、失敗に落ち込み、優秀な同期の三浦をやっかみ、やってられねぇと自棄になり、見習い期間のあいだ、悩み続けていた。
そんなとき、連続放火犯と対峙した三浦が大怪我を負う。聖大は、気持ちに迷いを抱えたまま、ひたすら犯人を追うしかなかった。
印象に残ったのは「人間なんて、汚いのが当たり前だ」という先輩刑事の言葉だった。人間誰もが持っている、その汚い部分を目の当たりにし、人間が嫌いになったり、人が信じられなくなったりしながら、それでも続けていこうと思えるのは「人間って、まんざら捨てたものじゃない」と思える瞬間があるからだと、まだ年若き、ほんの少しだけ先輩の刑事が、迷い悩む聖大に語るのだ。
新米巡査高木聖大シリーズは、今のところ2冊。次は『駆けこみ交番』です。
少し成長した聖大くんが登場する『いつか陽のあたる場所で』もおススメ。
『いちばん長い夜に』
乃南アサの小説、マエ持ち女二人組シリーズを読んでいた。全3冊で文庫化しており、短編を重ねていく連作短編集だったこともあり、一話読んではベッドに置いったままにしたり、銀行の待ち時間に開いたりと、のんびり読書に最適なエンタメ小説だと思っていた。前科持ちの女性達のストーリーだということに、現実世界から切り離されたファンタジーのような気楽さを感じていたのかも知れない。『いつか陽のあたる場所で』『すれ違う背中を』の2冊を読み終えても、そういう感覚は変わらなかった。ところが3冊目『いちばん長い夜に』の途中から、思いもよらぬ方向へと物語は進んでいったのだ。
主人公、芭子(はこ)は、綾香の生き別れた息子を探しに仙台を訪れた。まさにその日、東日本大震災が起こったのである。現実世界から切り離されたファンタジーの様相は、一変した。
作者、乃南アサは、綾香の故郷に設定した仙台の街を、日帰り取材にあてたその日に震災を体験している。芭子が体験したことは、そのまま自分が体験したことだと、あとがきにかかれていた。だからこそ、小説もこういうカタチになったのだろう。
罪を犯し、償い、それを背負って生きていく。そんなことは考えたこともなく、気軽に読み始めたシリーズだが、これはファンタジーではないのだと、読み終えて息苦しくなった。殺人を犯した綾香の心の闇を奥深くまで描き切った乃南アサは、もしも震災を交えなかったとしても、そこをぼかすことなく違うカタチでかいたのだろうと読み終えて確信を持った。
「過去のない人はいない」芭子が好きになった、南くんの言葉だ。
「わたしの失敗は、簡単に片づけられるものじゃない」
芭子は返すが、南くんの言葉だけが、心にいつまでもひっかかっていた。

『ボクの町』は、マエ持ち女二人組シリーズに登場する警官が主人公。
芭子に気があるみたいだけど、元気すぎてちょっとずうずうしくも感じられ、
嫌がられていました。今風のドジな若者と裏表紙には、かいてあります。
関係ないけど、紐栞がついてる文庫本っていいな。

主人公、芭子(はこ)は、綾香の生き別れた息子を探しに仙台を訪れた。まさにその日、東日本大震災が起こったのである。現実世界から切り離されたファンタジーの様相は、一変した。
作者、乃南アサは、綾香の故郷に設定した仙台の街を、日帰り取材にあてたその日に震災を体験している。芭子が体験したことは、そのまま自分が体験したことだと、あとがきにかかれていた。だからこそ、小説もこういうカタチになったのだろう。
罪を犯し、償い、それを背負って生きていく。そんなことは考えたこともなく、気軽に読み始めたシリーズだが、これはファンタジーではないのだと、読み終えて息苦しくなった。殺人を犯した綾香の心の闇を奥深くまで描き切った乃南アサは、もしも震災を交えなかったとしても、そこをぼかすことなく違うカタチでかいたのだろうと読み終えて確信を持った。
「過去のない人はいない」芭子が好きになった、南くんの言葉だ。
「わたしの失敗は、簡単に片づけられるものじゃない」
芭子は返すが、南くんの言葉だけが、心にいつまでもひっかかっていた。
『ボクの町』は、マエ持ち女二人組シリーズに登場する警官が主人公。
芭子に気があるみたいだけど、元気すぎてちょっとずうずうしくも感じられ、
嫌がられていました。今風のドジな若者と裏表紙には、かいてあります。
関係ないけど、紐栞がついてる文庫本っていいな。
HN:
水月さえ
性別:
女性
自己紹介:
本を読むのが好き。昼寝が好き。ドライブが好き。陶器屋や雑貨屋巡りが好き。アジアン雑貨ならなお好き。ビールはカールスバーグの生がいちばん好き。そして、スペインを旅して以来、スペイン大好き。何をするにも、のんびりゆっくりが、好き。
ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com
(☆を@に変えてください)
ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com
(☆を@に変えてください)
